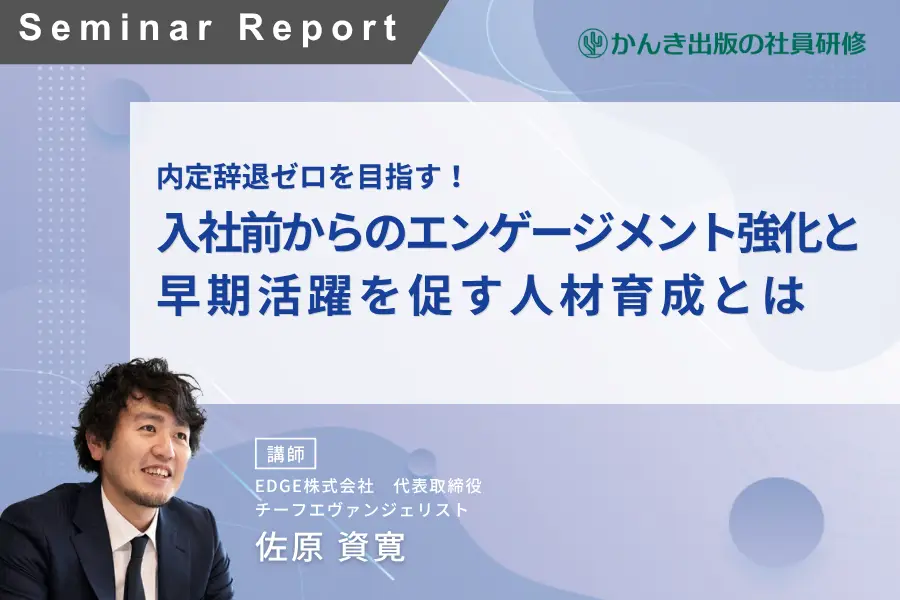
目次
2025年6月25日に『内定辞退ゼロを目指す! 入社前からのエンゲージメント強化と早期活躍を促す人材育成とは』と題した人事・研修ご担当者向けのセミナーを開催しました。
内定者支援プラットフォーム「エアリーフレッシャーズクラウド」を提供するEDGE株式会社代表取締役 チーフエヴァンジェリスト 佐原 資寛氏をお招きし、現代に適した内定者フォローと業務効率化のポイントをお話しいただきました。
セミナーの一部を抜粋・編集してご紹介します。内容は、講師の許可を得て掲載しております。
概要
近年加速する新卒採用の早期化・長期化により、内定者との関係構築はより複雑かつ重要な課題となっています。「内定を出して終わり」ではなく、入社まで、そして入社後の活躍まで見据えた戦略的なアプローチが求められます。内定辞退の防止に向けて、多忙な人事担当者の方でも、現実的かつ効果的なフォローのポイントをお話いただきました。
内定辞退防止と入社後の活躍を両立する「内定者フォロー」のアプローチを解説するにあたり、初めにEDGE株式会社のサービスを紹介します。
(詳細は以下リンク先ページをご覧ください。)
内定者支援プラットフォーム「エアリーフレッシャーズクラウド 」
https://edu.kanki-pub.co.jp/training/200
新卒採用の現状
 ではまず、今の新卒採用を取り巻く市況について、あらためて整理させていただきます。
ではまず、今の新卒採用を取り巻く市況について、あらためて整理させていただきます。
ご存じの通り、内定出しのタイミングは年々早まり、企業間での過当競争の様相を呈しています。早期に動き出さなければ内定承諾数の確保が難しくなり、採用が長期化してしまう。大手企業でさえ、夏以降の採用を継続せざるを得ない状況です。
このような中、早期に内定を出してもフォローが希薄だと、学生が就職活動を再開するリスクが高まります。特に優秀な学生ほど複数社から声がかかりやすく、承諾後の辞退リスクが顕在化しています。
さらに、採用活動の前倒しにより、翌年の新卒採用活動と現年度の内定者フォローが重なり、人事担当者の人的リソースがひっ迫する傾向が強まっています。新卒採用活動を優先し、内定者フォローが希薄になってしまう結果として、内定者との接点は薄くなり、企業側と不安感の残る学生側の温度感のギャップが広がっている――これが今の採用現場のリアルだと感じています。
辞退の理由と辞退防止に必要なフォロー
では、なぜ学生は内定を辞退するのか?
理由の多くは「他社の方が魅力的だった」という、いわば比較負けです。なかには防ぎようのない辞退もあります。たとえば第一志望企業の選考が後ろ倒しになり、御社を一旦承諾したが、本命企業に受かったら辞退する──これはもう不可避です。
しかし、防げる辞退も確実にあります。たとえば「不安が消えない」「社員と話せる機会がなかった」など、情報不足や孤独感が原因で辞退を選ぶケースです。
辞退を防ぐために大切なのは、「モチベーションを高めること」ではなく、「ピークから下がらないように維持すること」。内定を出した瞬間が、学生の入社意欲のピークです。そこから時間が経つごとに気持ちは自然と下がっていきます。その下げ幅をいかに小さくするか。そこにこそ、内定者フォローの本質があります。
私たちは3つの視点での対応をおすすめしています。
1. 内定者の状況を可視化
全内定者を同じ頻度・同じ内容でフォローするのではなく、辞退リスクを見極めて優先的にアプローチする必要があります。
2. 内定ブルーの防止
リアルな職場の様子、若手社員の体験談などを共有し、学生の中に「自分がここで働く」イメージを描いてもらうことが効果的です。
3. 効率的な個別対応
複数担当者間での対応履歴の共有、チャットによる気軽な相談窓口など、心理的ハードルを下げる仕組みも有効です。
具体的事例
ここからは、具体的にどんな取り組みが行われているのか、当社の支援実績をもとにした事例をご紹介いたします。
事例1:辞退リスクを可視化し、優先的なフォローを実現
ある企業様では、AIを活用して内定者の行動データから辞退リスクを3段階で可視化しています。ログイン頻度、アンケート回答速度、チャット返信率などを元に「要注意」「危険」「通常」と分類し、対応の優先度を明確化。リソースを集中させることで効率的な辞退防止につなげています。
事例2:アンケート活用で学生の志向や不安を早期に把握
就活振り返りアンケートを通じて、内定者の就活の経緯や比較ポイント、現在の心境を把握。正直な声が拾えることで、その後のフォロー内容を個別に設計することができます。特に他社と比較して迷っている学生に対しては、重点的にコミュニケーションの機会を設けています。
事例3:内定ブルー対策として「働くイメージ」を提供
「社会人として通用するか不安」という学生の声に対し、若手社員の仕事ぶりや配属後の様子を伝えるコンテンツを配信。任意参加の学習機会や、PCスキルの簡単な練習コンテンツも提供し、学生の安心感につなげています。
 事例4:若手社員によるリアルな声がエンゲージメントを高める
事例4:若手社員によるリアルな声がエンゲージメントを高める
内定者から評価の高かった施策のひとつが「若手社員からのメッセージ動画」。編集された広報動画よりも、素朴な職場の様子や日常風景をスマホで撮ったようなリアルな動画の方が、Z世代の心には響きます。企業が着飾らない姿を見せることで、信頼と親近感が生まれました。
事例5:複数担当者での一元管理で対応の質を担保
フォローを複数名で分担する企業様では、内定者ごとの属性・接点履歴をすべて一元管理。情報の食い違いや、内定者側の混乱を防ぐことに成功しています。学生とのやり取りを可視化するだけで、ちょっとした不信感を未然に防ぐことができています。
事例6:気軽に相談できる“接点”の設計
チャット機能を活用し、若手人事がフランクにやりとりすることで、内定者が本音を話せる場を作っています。特に他社選考の進捗や悩みごとを正直に話せる雰囲気づくりは、辞退防止に直結します。単純接触効果を活かしたつながりの維持が、信頼構築に大きく貢献しています。
〈番外編〉その他の企業の好事例
たとえばクライアント様(IT業界)では、内定前から現場社員を学生にメンターとしてアサイン。選考中から密なコミュニケーションをとり、内定後も継続的な関わりを持つことで、辞退率ゼロを実現しています。
また、別のクライアント様(メーカー)では懇親会をデータで設計。内定者が共感しにくい企業の魅力をテーマに懇親会を設計し、その後の共感度をアンケートで測定。効果検証を繰り返し、年々設計の精度を高めています。
さらにクライアント様(商社)の事例では、内定者に「次年度採用の説明会資料」を制作させるワークを実施。企業の魅力を自ら考え、アウトプットする経験は、自然とエンゲージメントを高める施策となりました。
まとめ
ここまで、入社後の活躍まで見据えた内定辞退防止の考え方と、具体的な取り組み事例をご紹介してまいりました。
重要なのは、「個別最適なフォロー」を実現するために、まず内定者の状況や心理を可視化すること。そして、辞退リスクが高い方には、きちんと工数をかけてフォローしていく――このメリハリが、今の採用環境では欠かせません。
また、内定ブルーを防ぎ、入社後の活躍につなげるには「リアリティのある情報提供」も重要です。理想だけでなく、実際の若手社員の姿や環境を見せることで、リアルな期待と安心感を育てていけます。
もちろん、「理想的なフォローをしたいけど、マンパワーが足りない」という企業様も多いと思います。そういった場合は、内定後のRPOや外部リソースの活用も、現実的な選択肢です。
大切なのは、辞退を防ぐことだけでなく、「活躍できる状態で入社してもらうこと」。ぜひ皆さんの会社に合った形で、無理なく実行可能なフォロー施策を設計いただければと思います。
質疑応答
Q:新人育成や早期離職防止にもつながる観点があれば教えてください。
A:やはり「現場配属後のOJT」が一番の鍵です。メンターに大きな負荷がかかり疲弊することで、新入社員にも悪影響を及ぼすことがあります。たとえば、メンターが孤立して悩まないよう、メンターと新入社員の日々のやり取りや日報を可視化する仕組みがあれば、上長や他の教育担当が早期にフォローに入れます。こうした職場全体で育てる体制が、早期離職を防ぐ上でも非常に効果的です。
Q:早期化によりフォロー期間が長期化していますが、内定者へはどのくらいの頻度で連絡すべきですか?
A:結論から言えば、「学生の状態による」です。月1回で十分な方もいれば、不安が強い学生には週1回でも足りない場合があります。一律対応では逆効果になることもあるので、まずは状態を把握して、必要な人に必要なタイミングで接点を持つ――これが基本になります。
関連情報
ご紹介しました内定者支援プラットフォーム「エアリーフレッシャーズクラウド」はこちらです。

参加者の声
- 個別に最適なフォローをするという点が印象的だった。
- 個別フォローの重要性は感じていたが、その通りだと思えた。
- 内定者の不安解消には、社員の様子を伝えることが大切だと理解できた。
お問い合わせ
ご相談は、下記フォームからお気軽にどうぞ。







