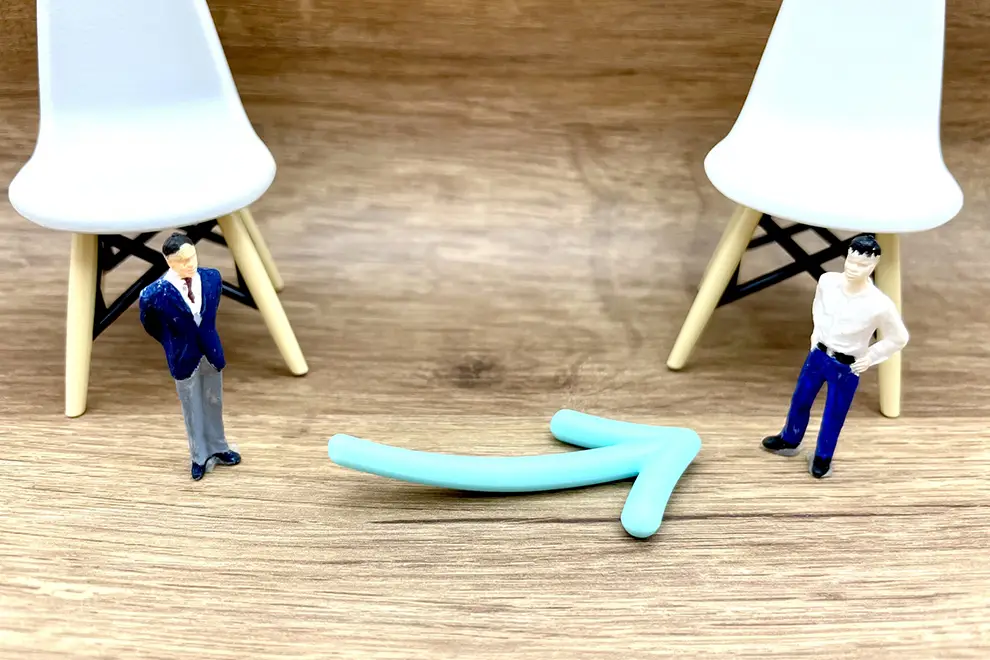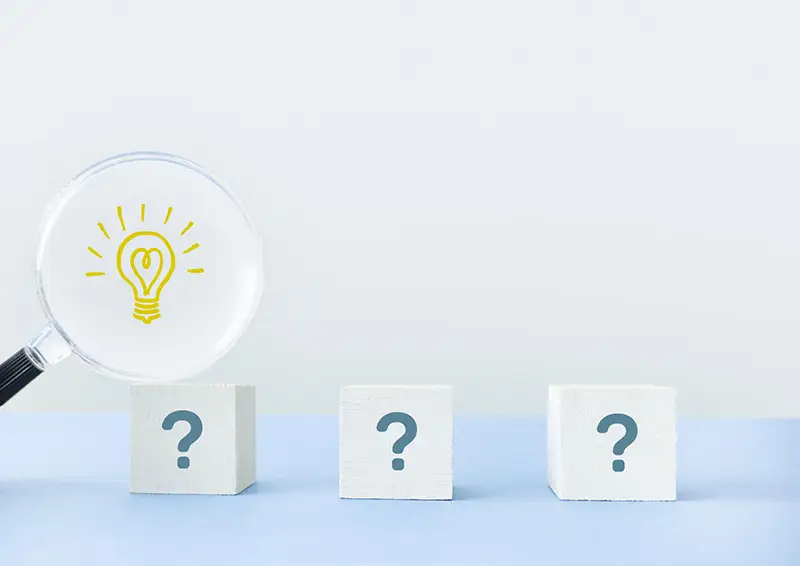目次
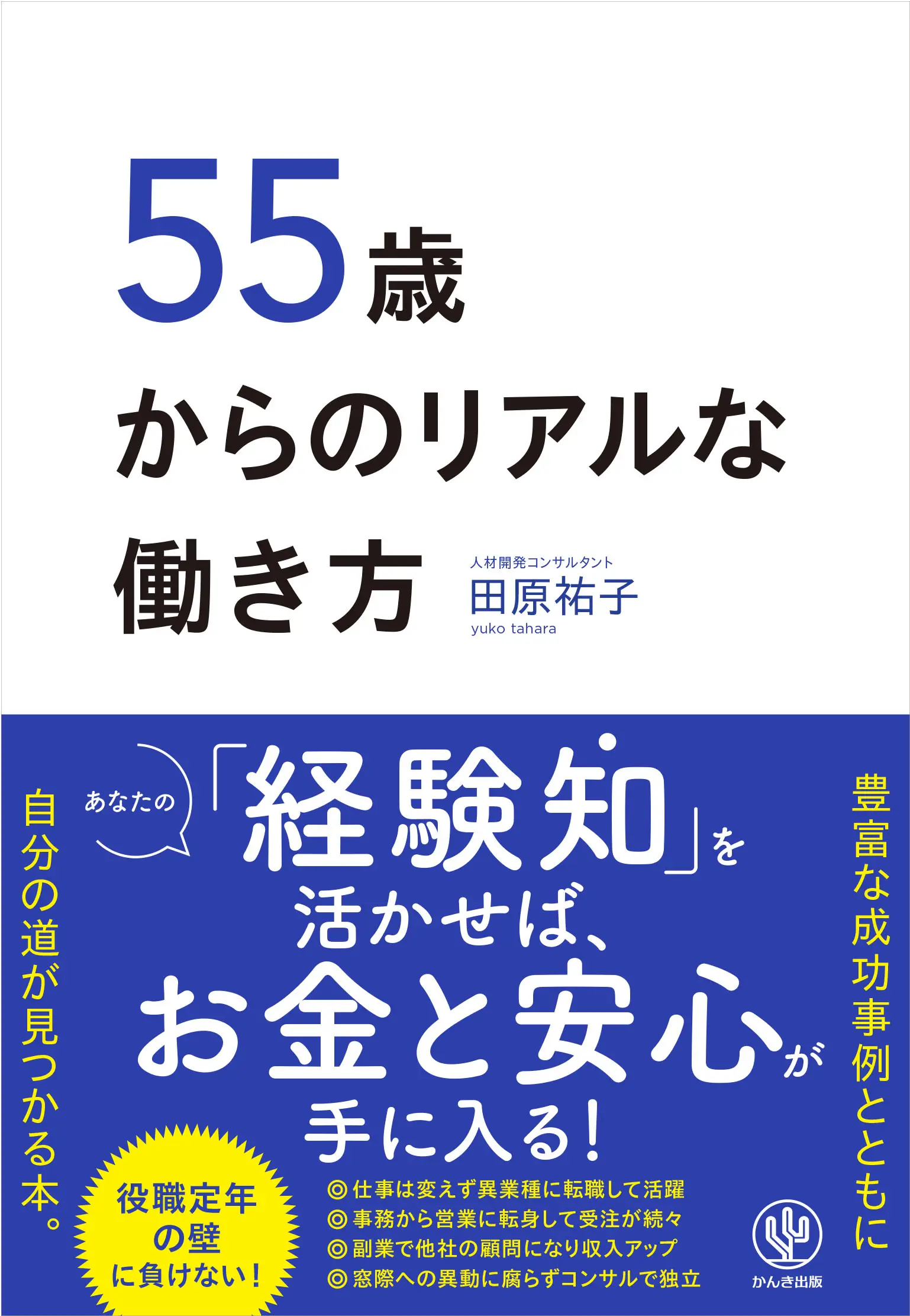 雇用の流動化や働き方の多様化が進む中、ベテラン層の退職やエース社員の転職等に伴い、長年培われた組織内のノウハウや経験知の消失、スキル継承の停滞が、多くの企業で問題になっています。 人生100年時代において、ミドル・シニア層が持つ「経験知(知識・スキル・コンピテンシー)」は、企業の競争力と成長力を左右する戦略的資産です。ところが、役職定年になったり、会社の中での役割が変わる頃からモチベーションやパフォーマンスが低下し、その価値が十分に活かされていないケースが少なくありません。 こうした背景から、リスキリングやキャリアの再設計を通じて、ミドル・シニアが再び高い成果を発揮できる仕組みづくりが求められています。 本コラムでは、書籍『55歳からのリアルな働き方』を要約し、ミドル・シニア社員を戦略的に活用するための実践的ヒントをご紹介します。
雇用の流動化や働き方の多様化が進む中、ベテラン層の退職やエース社員の転職等に伴い、長年培われた組織内のノウハウや経験知の消失、スキル継承の停滞が、多くの企業で問題になっています。 人生100年時代において、ミドル・シニア層が持つ「経験知(知識・スキル・コンピテンシー)」は、企業の競争力と成長力を左右する戦略的資産です。ところが、役職定年になったり、会社の中での役割が変わる頃からモチベーションやパフォーマンスが低下し、その価値が十分に活かされていないケースが少なくありません。 こうした背景から、リスキリングやキャリアの再設計を通じて、ミドル・シニアが再び高い成果を発揮できる仕組みづくりが求められています。 本コラムでは、書籍『55歳からのリアルな働き方』を要約し、ミドル・シニア社員を戦略的に活用するための実践的ヒントをご紹介します。
これからは、「経験知や才能・スキル」で稼ぐ時代
多くの企業で導入されている「役職定年」制度。50代半ばごろの年齢を境に、多くのミドル・シニア社員がキャリアの大きな分かれ道に立たされています。かつての「悠々自適なセカンドキャリア」というイメージは過去のものとなり、年収減とモチベーション低下という厳しい現実に直面しているのが実情です。
ダイヤ高齢社会研究財団資料「50代・60代の働き方に関する調査報告書」(2018年)によれば、役職定年後の年収は9割以上の人が減少し、そのうち4割は半減以下となっています。さらに深刻なのは、約7割の社員が異動なく以前と同じ職場で同じ仕事をしているにもかかわらず、半数以上が「モチベーションが下がった」と回答している点です。元部下が上司になる気まずさや、権限を失ったことへの不満も聞かれます。
残りの約3割の社員は、同じ企業内で所属異動して働いていますが、その場合でも、「それまでの知識・技能・経験が活かせなくなった」「やりがいの持てない職務になった」といった新たな課題が生まれています。どちらのケースにも共通しているのは、企業にとって最も価値あるはずの、長年培われた専門的な「経験知」が十分に活かされていない、非常にもったいない状態であるということです。
この課題を解決する鍵が、社員自身も気づいていない「経験知(知識・スキル・コンピテンシー)」と「才能(強み)」です。これらは、若手社員がITリテラシーで勝っていたとしても、ベテランの経験知に裏打ちされた仕事には足元にも及びません。
ミドル・シニアにとって、これからは「経験知や才能・スキル」を活かして働くことで稼ぐ時代です。 経験知の可視化は、当人のモチベーション回復だけでなく、組織内のスキル継承・戦略的配置にも直結します。
ミドル・シニア層は、AIにはない「自分の強み」を知っているか
ミドル・シニアの社員は自分の「極上の宝物=経験知」に気づいていない
ミドル・シニアの社員の中には、本人が気づいていない、素晴らしい「極上の宝物=経験知」が眠っています。それは、若手社員が今から追いつこうとして、死ぬほど頑張って働いても、決して手が届かない「ミドル・シニアの社員にしかない特別な宝物」です。この経験知は、「単なる知識」のことではなく、経験や学びを通じて獲得される知識であり、仕事において大きな価値を生み出します。
また、昨今は、生成AIが目覚ましい進化を遂げていますが、AIは身体を持たず経験を積むことができないため、今こそ、人間の経験知や、仕事をするスキルが注目されているのです。
具体的には、経験知は以下の3つで構成されています。
①専門分野=知識・領域
②実践スキル=業務経験
③コンピテンシー=行動特性・人間性
長年ミドル・シニアが苦労して経験した失敗や成功、そして、万一の時には即座に判断する判断力など、すべて無形の資産として蓄積されたものが、かけがえのない「経験知」であり、AIは苦手とする今後これらの価値はますます注目されてくることでしょう。
ところが、多くの方が「自分自身に内在する才能に気づいていない」という問題があります。
パーソル総合研究所らの調査では、定年後の再雇用に備え、「専門性が重要」であると解説されていますが、それにもかかわらず「専門性を深める」「専門性を広げる」努力をしている人はたった2割しかいません。この「専門性」とは、まさにミドル・シニアの宝物である、知識・スキル・コンピテンシーであり、経験知に他なりません。
自分の強みは、これまでしてきた「仕事」と「経験」の中にある
「今の肩書や役職がなくなってしまったら、どんな仕事ができるんだろう?」
「自分は○○の分野専門でやってきたので、他の仕事はできそうもない」
このような嘆きを耳にすることがありますが、ミドル・シニア層の社員は会社と一体化しているわけではなく、さまざまな才能を持つ、一人の素晴らしい貴重なタレント(人材)です。
ある地方新聞社の記者のTさんは、「記者っていう仕事は潰しが効かない」と思い込んでいました。しかし、それはTさんがご自身の宝物、経験知や才能に長年気づかず、自己分析できていないだけなのです。彼の経験を知識・スキル・コンピテンシーに細かく棚卸しすれば、記者以外にも、社内外の多様な仕事ができる可能性を持ち合わせていることがわかります。これまでのスキルを活かして、新たに生成AIのハルシネーションを見破ることもできるかもしれません。
※無形資産:知識・スキル・コンピテンシーという見えない資産のこと
(1)知識
・新聞社の業務全般に関する知識
・情報の収集データ・分析に関する知識
・これまで記事を書いてきた、さまざまな業界に関する知識
(2)スキル
・記事を書くスキル
・情報を収集するスキル
・情報の真偽を見極めるスキル
(3)コンピテンシー
・事実に基づいて記事を書くという誠実さ
・課長として、部下を育成する責任感
・新聞を編集する際、全体のバランスを考えるバランス感覚
「無形資産」は、人生100年時代を生き抜く最強の武器
一般的に「資産」というと金融商品などをイメージしがちですが、これら目に見える「有形資産」は、いつかはなくなってしまいます。会社や肩書、役職などもすべて有形資産です。一方、どんな時代になろうとも、なくならない資産が「無形資産」であり、これこそが経験知(知識・スキル・コンピテンシー)に他なりません。
この無形資産は、人生100年時代を生き抜くための「最強の武器」と言えるでしょう。ただし、無形資産は価値が見えない資産であるからこそ、ミドル・シニア層の方々自身が、自らの資産価値に気づき、それを表現していくことがポイントになります。
脳は「鍛え続けければ120歳まで成長する力を持っている」とされており、特に50代は「実行力」や「判断力」を司る脳の部位が発達し、「人間力も高まってきた熟年からこそが、脳が最も輝く年代」だと言います。また、昨今話題の「生成AI」の時代においても、私たち人間にはAIにはない、「人間としての判断力」という最大の暗黙知、すなわち「人間ならではの強み」があるのです。
「経験知」を、組織の資産と未来のキャリアに変える4つのステップ
新しい未来のキャリア戦略・4つのステップ
ミドル・シニア層の社員一人ひとりが、経験知を棚卸しすることで、「新しい未来のキャリア」を創っていくことが可能です。
また、これらは、組織や若手の育成にとっても非常に重要な指導の道しるべともなるのです。
| ●STEP1 見える化 & 分解する | 知識・スキル・コンピテンシーを明らかにする |
| ●STEP2 キャリア戦略 | ありたい自分を「4象限」から選択する |
| ●STEP3 収入戦略 | 希望する収入の4つの目標ゾーンを選択する |
| ●STEP4 出口戦略 | 身の振り方を考える、経験知を活かす |
●STEP1 見える化&分解する 知識・スキル・コンピテンシーを明らかにする
STEP1では、ミドル・シニアの経験知である「知識・スキル・コンピテンシー」を見える化していきます。
経験知の言語化❶―1 「専門分野=知識・領域」を活かす
まず、これまで経験してきた仕事の分野を振り返り、それぞれで得た知識を具体的に書き出します。単に「営業」とまとめるのではなく、「法人向けか個人向けか」「どんな顧客層か」など、できるだけ細分化し、一人ひとりが自分ならではの専門性を明らかにします。ここで重要なのは、「経験を通じて得られた知識」がいかに深く、実践的であるかという点です。長年の経験や実践の蓄積により、知識は深化・進化しているのです。
経験知の言語化❶―2 「実践スキル=業務経験」を活かす
次に、実際の業務を通じて身につけたスキルを整理します。単に業務の種類ではなく、実践スキルは、これまで「何をしてきたか」という経験や、具体的に仕事で「何を」「どのように」できるのか、という能力のことを指し、「役職・役割」もあります。
細かく書き出すことで、抽象的な職務記述では伝わりにくい「使えるスキル」が見えてきます。一人ひとりが自身の潜在的な可能性や、やってみたいこと、また市場価値の高い「メタスキル(どの部門にも転用できるスキル)」の存在に気づくことができます。
経験知の言語化❶―3 「コンピテンシー=行動特性・人間性」を活かす
コンピテンシーとは、行動特性や人間性という意味です。その人の行動や仕事の成果は、潜在するコンピテンシーによって大きく異なることを意味しています。
ここでは、どんな価値観で仕事に取り組んできたか、どんな場面で信頼されたかなど、定量化しづらいけれど確実に存在する「働きぶりの質」を可視化します。たとえば「部門を超えて協働できる力」や「教えることが得意」といった要素は、次のキャリアの大きな武器になります。
●STEP 2 キャリア戦略 ありたい自分を「4象限」から選択する
これまでの経験知を明らかにし、新たな可能性を見つけてどう伸ばすかという観点から、これまでの枠組みに縛られない、多様で自在なキャリア戦略を立てていきます。
具体的には、
① キャリアアップ:同業種×同職種
② キャリアシフト:同業種×異職種
③ キャリアチェンジ:異業種×同職種
④ キャリアチャレンジ:異業種×異職種
という4通りのキャリアタイプから、最も心に響くパターンを選択します。4つのパターンで、新たなキャリアの可能性を探る中で、どのような知識やスキルが必要なのかが明確になります。
●STEP 3 収入戦略 希望する収入の4つの目標ゾーンを選択する
役職定年後などで副業OKの企業であれば、個人のライフスタイルや目標に合わせて、4通りの目標ゾーン(これまでの6割の収入、これまでの8割の収入、これまでと同じ収入、これまで以上の収入)の中から選択し、必要な収入戦略を立てます。
●STEP 4 出口戦略 身の振り方を考える、経験知を活かす
「どのような仕事を、どのようなスタイルでしていくか」という「キャリアを活かすところ」を決めます。主に4つのパターン(今の会社に残る、副業する、転職する、起業する)が紹介されています。
本コラムでは、『55歳からのリアルな働き方』から一部抜粋して、ミドル・シニア層の戦略的活用についてご紹介しました。これらの内容は、ミドル・シニア向けのキャリア開発支援でありながら、企業側にもノウハウ継承と組織の持続的成長を支える実践策として効果的に活用できます。
弊社では、ミドル・シニア層の暗黙知を可視化し、組織活性化につなげる「暗黙知見える化プログラム」研修・eラーニング講座・ワークショップなどをご提供しております。ベテラン社員のモチベーション低下やノウハウの継承などに課題をお持ちの企業ご担当者様は、ぜひお問い合わせください。
お問い合わせ
ご相談は、下記フォームからお気軽にどうぞ。

■ 関連プログラム