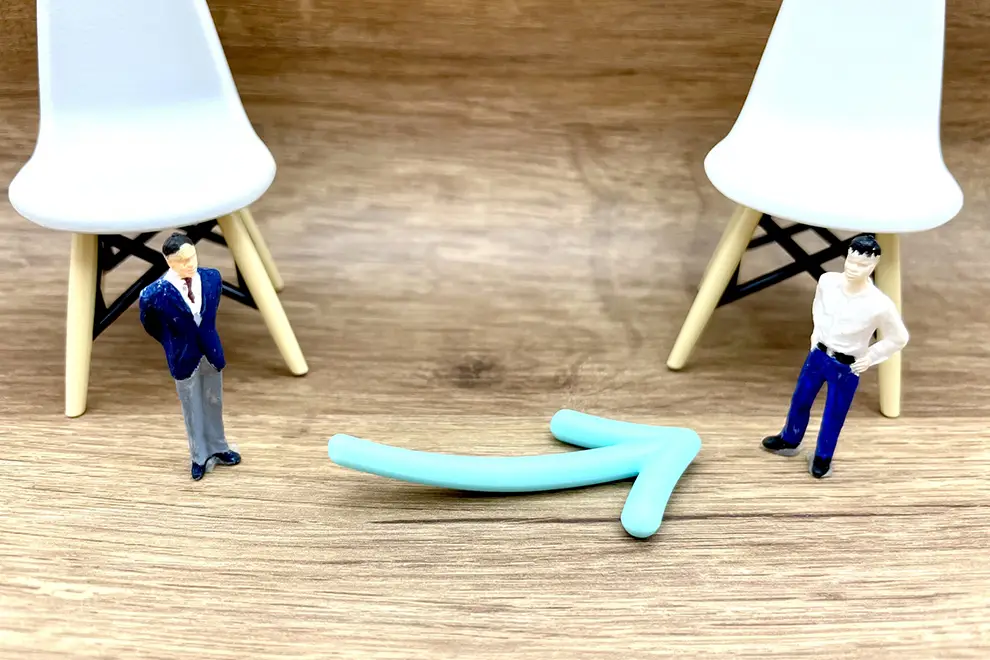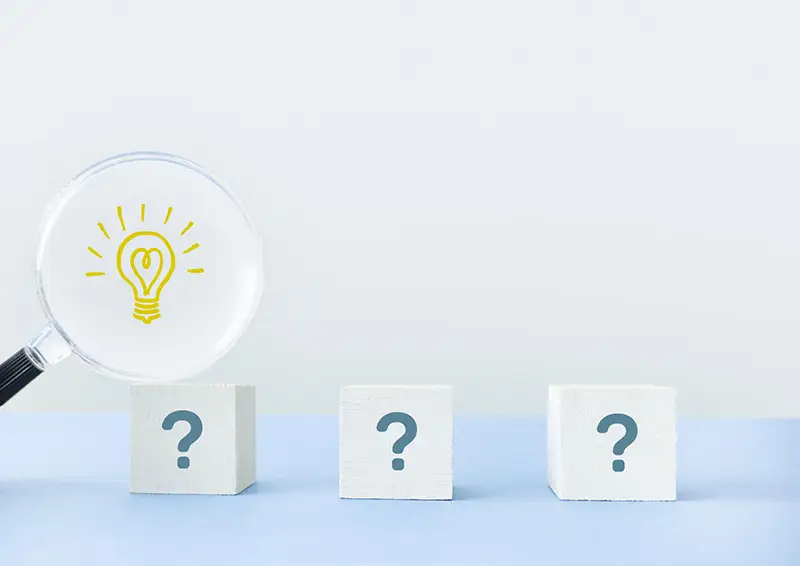目次
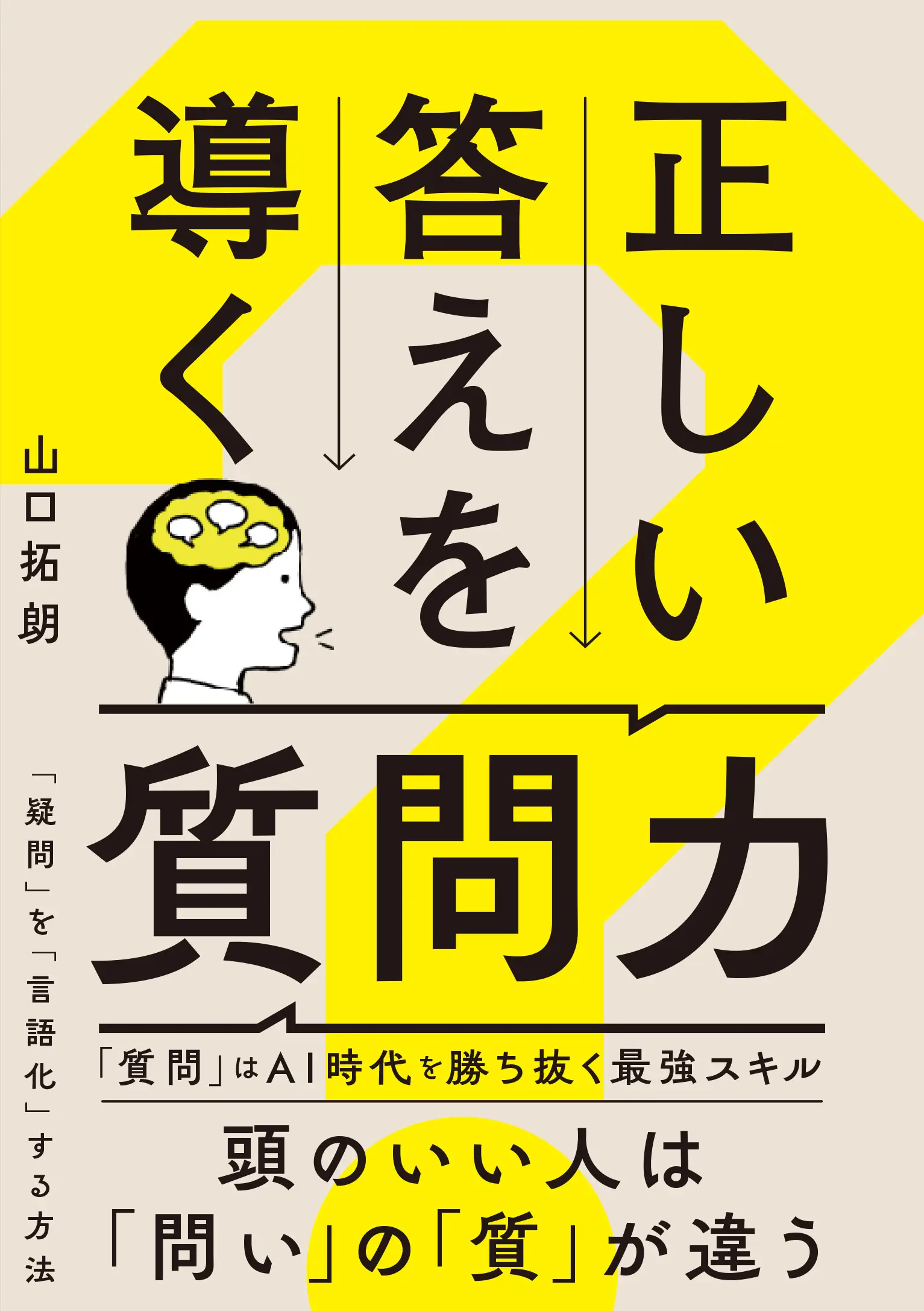 「若手社員が会議で発言しない」「社員が指示待ちで自ら考えない」「AI導入したが活用できていない」といった課題はありませんか?また、AIなどの最新技術が普及する今、「AI導入したが活用できていない」という声も多く聞かれます。
「若手社員が会議で発言しない」「社員が指示待ちで自ら考えない」「AI導入したが活用できていない」といった課題はありませんか?また、AIなどの最新技術が普及する今、「AI導入したが活用できていない」という声も多く聞かれます。
その原因のひとつは、“問いの質”にあるかもしれません。 これらの課題を解決する上で、「質問力」が一つの鍵となります。質問力は単なるコミュニケーションスキルではなく、個人の「仕事のレベル」と密接に関連する、組織成長の必須要件です。質問力を磨くことは、そのまま「仕事力」を磨くことにつながります。
本コラムでは、書籍『正しい答えを導く質問力』を要約し、「質問力」を磨くことで、思考を整理して判断力・行動力を高め、成果創出だけでなく、個人と組織の成長につなげるヒントをご紹介します。研修導入をご検討されている方は、ぜひお読みください。
質問力とは何か?
質問は、単に情報を得るための手段ではありません。人の心を開き、対話を深め、信頼を築く力を持ちます。また、質問力はあなた自身の能力、すなわち 「思考力」「判断力」「探究力」「発想力」「言語化力」「読解力」、そして 「コミュニケーション力」 の全てを引き上げます。これらはすべて「いい問い」を持てるかどうかにかかっているのです。
質問とは、漠然とした「疑問」(なんとなく気になる、腑に落ちないといった感情)を、「意味のある問い」へと変換する 「目的ある言語化」 の行為です。この力は、知性、感性、論理性、想像力などを総動員して発揮される、きわめて総合的なスキルであり、限られた人に与えられた「才能」ではなく、誰でも磨いていける 「技術」と「心構え」 なのです。
なぜ今、「問い」が最重要なのか?
世界を変える発見の出発点は、ニュートンが「なぜリンゴはまっすぐ下に落ちるのか?」と当たり前の現象に疑問を抱いたように、「なぜ?」という問いでした。この《問いを立てる力》は、変化や成長、進歩の起点となります。
特に、正解が存在しない不確実性の時代において、質問は進むべき方向性を決める羅針盤の役割を果たします。マネジメントの父、ピーター・ドラッカーは「間違った答えよりも、間違った問いのほうがはるかに危険だ」と述べており、「正しい問いを立てること」こそが本質であると教えています。この力は、当たり前や常識を疑い、目の前の《前提》を問い直す意識から生まれます。
「質問力」はAI時代を生き抜くための最強の武器
AIが急速に普及する現代において、質問力は生存戦略の核となります。AIは、与えられた問いに忠実かつ高速に答えますが、その回答が本当に役立つかどうかは、すべて「問いの質」にかかっています。
質問力の乏しい人が「なんとなく」でAIに入力してしまうと、ありふれた答えや、ピントのずれた答えしか得られません。生成AIは、ゴミを入れたらゴミが出てくる(GIGO:Garbage In, Garbage Out)という大原則が適用されます。
一方、質問力のある人は、目的と狙いを持って最適な入力を設計することで、理想的、あるいは予想を超えた答えを引き出すことができます。AI時代に求められるのは、「答えを出す力」ではなく、「問いを立てる力」なのです。
思考を動かし、進むべき方向を決める質問の本質
質問は、単に情報を引き出す手段ではなく、自分と相手の思考を活性化させ、行動へと導く「知的ツール」です。質問の持つ本質的な力は以下の通りです。
本質① 質問は思考を動かす
質問されると、人の脳は意識的にも無意識的にも、答えを探し始めます。
本質② 質問は思考の方向性を決める
「なぜ失敗したのか?」と問うか、「どうすれば成功できるか?」と問うかで、思考はまったく違う方向へ進みます。
本質③ 質問は「価値観」や「判断軸」を浮かび上がらせる
例えば、「なぜその選択をしたのか?」と問うことで、質問を受ける側の優先順位、価値観、判断基準などが見えてきます。
本質④ 質問は「場の空気」すら変える
沈黙をほぐしたり、行き過ぎた熱をクールダウンさせたり、議論にリズムや方向性を与えたり。質問には、その場の「温度」や「空気感」をマネジメントする力があります。
本質⑤ 質問者が主導権を握る
多くの場合、質問者は、回答者よりも、立場的に優位に立ちやすくなります。なぜなら、(良くも悪くも)質問によって相手の時間・思考・行動をコントロールすることができるからです。
質問は単なる会話の道具ではなく、「質問を受ける側の思考を動かし、その場の空気感をデザインする役割」も担っています。うまく使うことで、仕事や人間関係で成果を出しやすくなります。
質問力は仕事力そのもの:成果直結型の思考基盤を構築する
では、質問力は、仕事にどのように活かせるのでしょうか。優れた質問ができる人材ほど、状況や情報を正確に把握し、物事の本質を捉える力に長けています。
質問力の高い方は、次の4つの共通点があります。
- 主体性・能動性: 自ら問いを設定し、学びや気づきを得て、視野を広げる力。
- 状況・文脈把握力: 読解力、観察力、推察力を総動員し、必要な情報を引き出す精度高い問いを立てる力。
- 目的意識の明確さ: 常に「何を得たいのか」「それをどう活かすのか」という目的意識を持ち、粘り強くやり取りする力。
- 簡潔かつ論理的な構成: 相手が答えやすいよう、無駄なく要点を明確に伝える力。これは相手への敬意と配慮の表れでもあります。
質問力を磨くことは、そのまま「仕事力」を磨くことに直結するのです。
人を育て、導く「リーダーの質問術」
上司が部下からの質問に安易に指示を与えるだけでは、部下は「指示待ち人間」になり、主体性や判断力が育ちません。上司に求められるのは、答えを与えるのではなく、「本人に考えさせる問い」を投げかけることができるリーダーシップです。
「指示待ち」だけでなく、「会議で発言が停滞する」「本音を言えない」といった、心理的安全性の課題解決にも、リーダーの質問術が不可欠です。
相談や質問を受けた場面で重宝するのが《コーチング質問》です。コーチングの基本は、相手の主体性を引き出し、自ら考え行動できるよう促すこと。
コーチング質問の代表例:
- 原因を考えさせる:どうしてそうなったと思う?
- 未来を予測させる:この先、どうなると思う?
- 解決策を考えさせる:どうしたら解決できそう?
- 主体性を促す:このプロジェクトをどうしたい?
- 目標を明確にする:ゴールをどこに設定する?
このプロセスを経ることで、短期的な問題解決だけでなく、長期的な成長へと導くことができます。
メンタルマネジメントに効くリフレーミング質問
質問は、相手の思考を動かす起爆剤です。特に相手が悩みや困難に直面しているときに有効なのが、《リフレーミング質問》です。
《リフレーミング質問》とは、物事の見方を変えることで、現状に対する「意味づけ」や「捉え方」を柔軟にし、前向きな気づきや行動を引き出すための質問です。
リフレーミング質問の例:
- 意味の再定義型:相手のネガティブな意味づけを、学びや成長の視点に変えます。
- 時間軸の転換型:視点を「今」から「未来」にずらして、状況を俯瞰させます。
- 他者視点の導入型:尊敬する人や第三者の視点を借りることで、思考を柔軟にします。
また、気づき誘発質問(目標や動機を振り返らせる質問や、経験を次へどう活かすかを問う質問)を通じて、部下の成長と前向きな姿勢を促します。大事なのは、問いかけを通して自分の頭で考えさせ、深い気づきを引き出すことです。
生成AIのポテンシャルを引き出す質問力
いま、生成AIを使いこなせる人と使いこなせない人との差を決定づけているのが、“質問力=プロンプト設計力”です。
AIの力を最大限に引き出すには、私たちが「何を求めているか」を明確な言葉で伝える力が不可欠です。
生成AIを使いこなすには、「的確に問いを立てる力」が求められ、問いの精度が高まるほど、AIからの情報提供の質も高まります。
生成AIへの問いかけ――「プロンプト設計」の基本
- 目的(ゴール)の明確化 :「何を知りたいか」を明確にする
- 読者の明確化: 「誰に向けた情報か」を伝える
- 背景・前提の明確化: AIが適切な《文脈》を捉えやすくなる
- 制約・条件の明確化: より現実的で実行可能な提案が得られる
- 出力形式の明確化: 実用的な成果物が得られる
- サンプルの提示方法: お手本を示すことで、意図やイメージに近づけられる
- 具体的に(抽象的に)指示する: イメージが明確な場合は具体的に、新しい視点や発想を求めたいときは、あえて抽象的な指示
- 生成AIと対話しながら内容を練り上げる: 「もう少し深く」「別の角度から」と対話を重ねる
企画書、プレゼン台本、契約書、業務手順書など成果に直結するビジネス文書の草案をAIに作らせる際も、これらの質問設計術に基づいた具体的な指示(プロンプト)が必要です。
情報を扱う際、一つの生成AIツールの回答だけで判断するのはリスクを伴います。情報の正確性や網羅性を高めるには、同じ質問を複数のAIツールに投げて比較する《多重質問》が有効です。
また、「最初のプロンプト」だけでなく、本当に価値あるアウトプットへと昇華させるには、出力後の問い直し=磨き直す力」を持ち、AIに質問を重ねて高品質へと磨き上げる姿勢が必要です。
本コラムでは、『正しい答えを導く質問力』から一部抜粋してご紹介しました。質問力を磨くことで、必要な情報を的確に引き出せるようになり、AIや最新テクノロジーを使いこなすための土台も築けます。
個人が仕事の成果を高めて成長するだけでなく、組織全体の成果も変えるスキルです。
著書である山口拓朗氏は、企業研修の講師としても豊富な実績がございます。「ビジネス文書研修」、「“要約力”向上研修」など実践的な研修プログラムもご用意しております。問いを立てる思考力や、言語化・説明力の強化に課題をお持ちの企業様は、ぜひお問い合わせください。
お問い合わせ
ご相談は、下記フォームからお気軽にどうぞ。