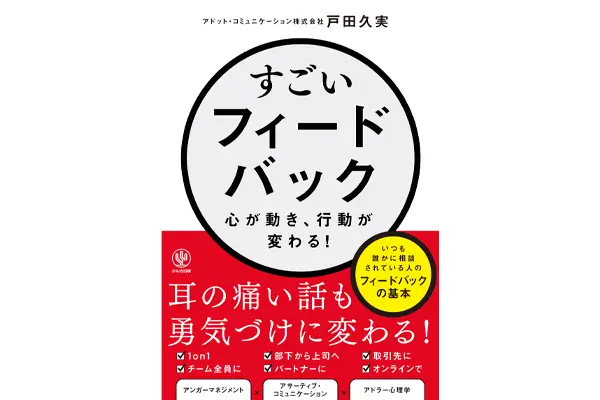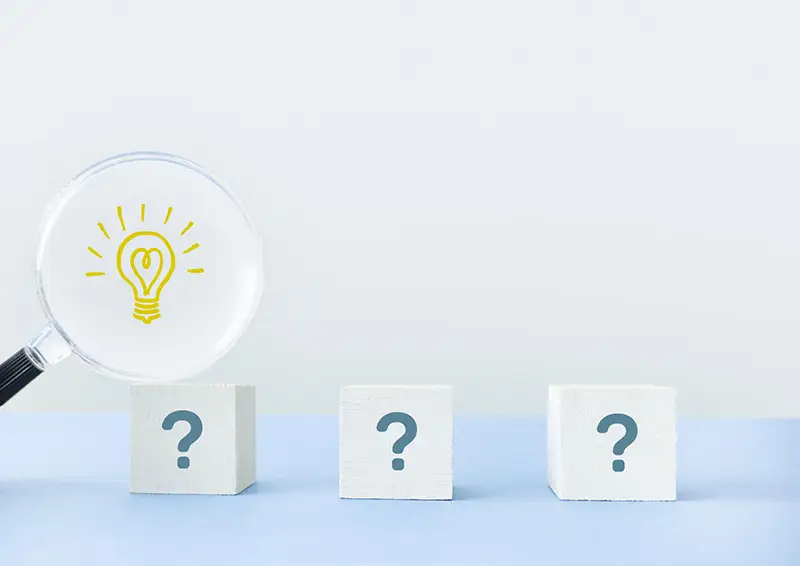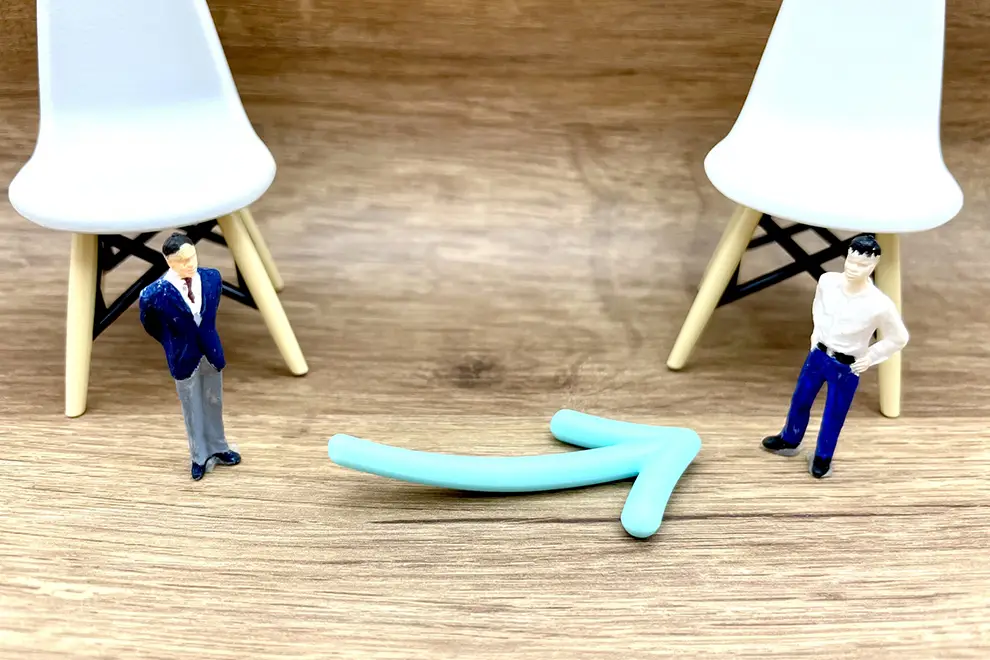
目次
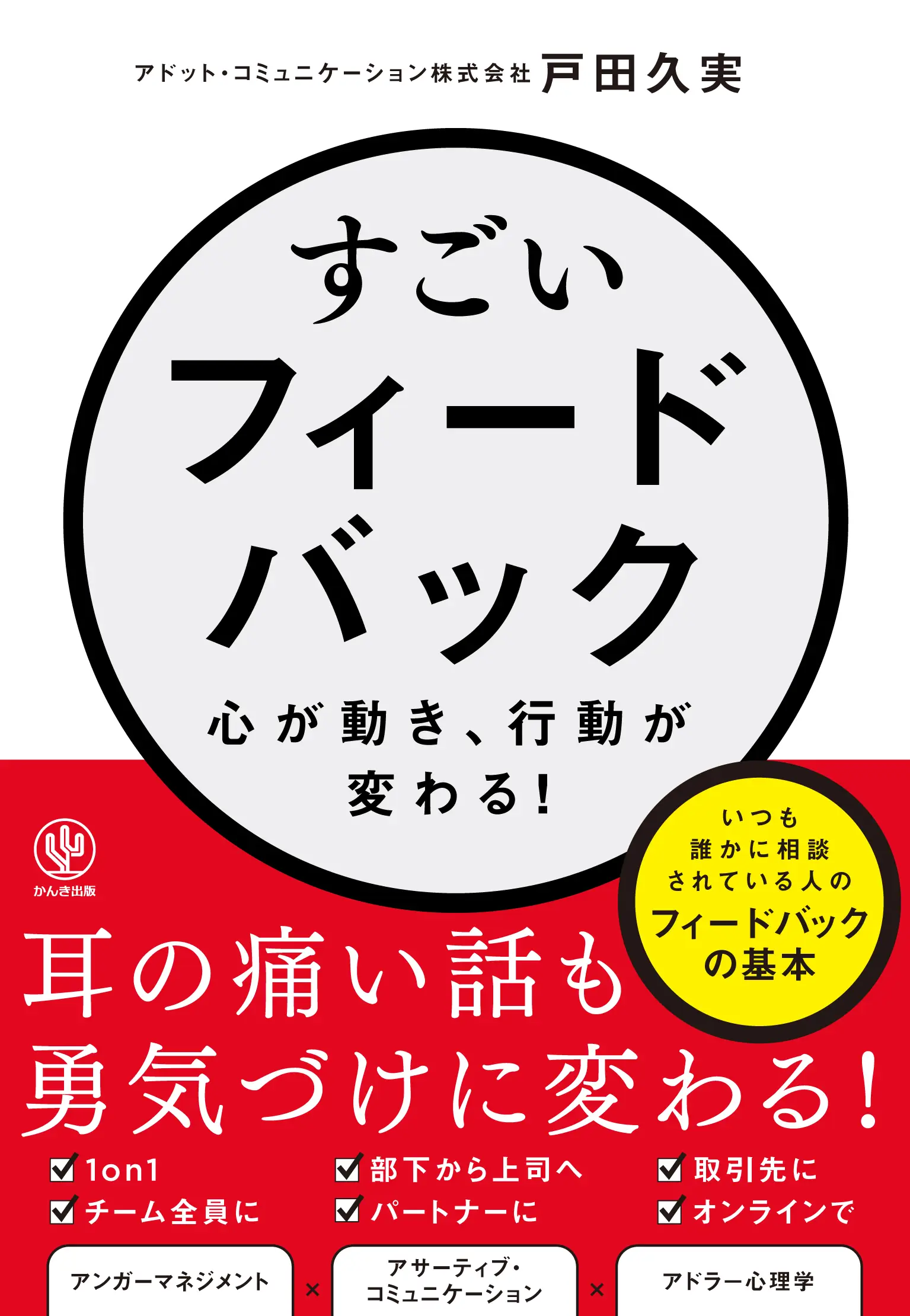 「フィードバック」と聞くと、どのようなイメージをもたれますか?
「フィードバック」と聞くと、どのようなイメージをもたれますか?
多くの方が「ダメ出し」「耳の痛いこと」といったネガティブなイメージを持たれるのではないでしょうか。日々の指導や1on1といった場での上司から部下への指導が、単なる「お説教や小言」や「指摘」だけで終わってしまい、結果として部下の成長やモチベーションアップに繋がらない、あるいは、感情的にならずに建設的な対話が難しい、といった声は少なくありません。
これらの課題を解決する鍵となるのが、本書が提唱する「すごいフィードバック力」です。
この手法は、単なる話し方(コミュニケーションスキル)にとどまらず、組織の停滞や人間関係の摩擦といった組織課題を解決し、チームの成果を大きく伸ばすために不可欠なものです。
フィードバックの目的は、次にどうすればいいか、相手にわかるように伝えることにあります。
本書で解説されるフィードバック手法は、アンガーマネジメント、アサーティブ・コミュニケーション、アドラー心理学という、確かな3つの理論をベースに構築されており、実践的なノウハウと心構えをご紹介しています。
組織内の良好な関係性を築き、メンバーが自発的に成長できる風土醸成へのヒントとなれば幸いです。このフィードバック手法は、社員一人ひとりとチーム全体の成長を促し、やる気を高めます。その結果、信頼関係が強化され、組織全体の成果を最大化することにつながります。
貴社の人材育成、管理職研修への導入をご検討されている担当者様は、ぜひ最後までお読みください。
1. 組織の成長を担保する3つの理論
本書で解説されるフィードバック手法は、感覚論ではなく、以下の三つの権威ある理論をベースに構築されています。これにより、研修や育成プログラムとして導入する際の信頼性と再現性が担保されます。
1-1. アンガーマネジメント:怒りと上手く付き合うための技術
1970年代にアメリカで開発された、怒りと上手に付き合うための心理トレーニング。怒らないことを目指すのではなく、「あのとき怒らなければよかった」「あのタイミングで怒っておけばよかった」というように怒りで後悔しないことを目指す。
怒ること自体は、悪いことではない。「部下(上司)はこうあるべき」など、怒りは「べき」がその通りにならないときに生まれる。自分の怒りの元になる「べき」を把握しておくのも重要。
1-2. アサーティブ・コミュニケーション:率直で対等な自己表現
アサーティブ・コミュニケーションは、相手と対等に向き合いながら、自分の意見や要求、感情を素直に率直に伝えることを目指す自己表現のタイプです。
攻撃的な自己表現や、非主張的な自己表現を避け、意見や価値観に相違があったとしても、相手の話に耳を傾ける双方向のコミュニケーションを大切にする姿勢が求められます。
1-3. アドラー心理学:勇気づけと共同体感覚
アドラー心理学は、「勇気づけの心理学」と言われています。勇気づけとは、困難を克服する活力を与え
ること。アドラー心理学が目指すのは、職場などで「自分はその一員だ」という共同体感覚を持つことです。共同体感覚を持つ社員は、周囲と互いに尊敬し合い、積極的に他者貢献しようとします。
2. 成長を促し、成果につながる「フィードバック」
フィードバックは、単なる「ダメ出し」で終わらせてはならず、相手の成長と信頼関係の構築を目指すものです。特に日本の大企業の人事担当者様が注力すべき、部下やメンバーのやる気を引き出し、不要な摩擦を避けるための具体的なポイントを紹介します。
フィードバックを受けることで、3つのことが得られます。
1 個人やチームの成長や改善につながる
2 課題を乗り越える勇気づけになる
3 気づかなかった新たな視点、学びの提供になる
フィードバックを受ける人には、多くの気づきが生まれます。だからこそ、「フィードバック=相手へのギフト」になるのです。
2-1. フィードバックの5つの心構え
1. 主役は相手: フィードバックは上司の不満をぶつける場ではありません。相手が「理解しやすい」「受け取りやすい」「実行しやすい」ことを常に意識し、相手の成長のために伝えることが大前提です。
2. 相手と対等に向き合う:年齢、キャリア、立場の上下に関わらず、心の中では常に相手と対等な関係(横の関係)を築くことが大切です。年上の部下へのフィードバックでも必要以上に謙り、忖度しない姿勢が求められます。
3. 素直に率直に伝える: 嫌われたくない気持ちから前置きが長くなったり、まわりくどくなったりすると、「結局何が言いたいのかわからない」状態に陥ります。ポジティブフィードバックもネガティブフィードバックも、率直に伝えることが大切です。
4. 自分の考えを俯瞰して見る: 自分の好き嫌い、思い込み、一時的な感情に左右されないよう、考えを整理し、感情的な偏ったフィードバックを予防することが重要です。
5. 自らもフィードバックのよき受け手となる: 自分が素直に耳の痛い意見を聞き入れる姿勢を示すことで、周囲もあなたのフィードバックに耳を傾けるようになります。また、ポジティブフィードバックに対して過度な謙遜は相手に気を遣わせるので気をつけましょう。
2-2. フィードバック時の7つの実践ポイント
1. 禁止形ではなくリクエストとして伝える: 「〜しないでください」といった禁止の言葉は使わない。代わりに、「今後〜してほしい」という要望、すなわちリクエストとして具体的に伝えましょう。
2. 事実と主観を切り分けて伝える:いきなり主観で伝えると「勝手に決めつけられた」と受け取られ、トラブルの原因になります。まず相手も認める事実を確認し、主観は「私はこう感じた/こう見えた」という表現で伝えましょう。
3. 結果だけでなくプロセスにも目を向ける: たとえ100%の結果が出なくても、それまでの過程・プロセスを評価するポジティブフィードバックを行うことで、部下のモチベーションアップにつながります。
4. ほかの人とではなく、その人自身の過去と現在を比較する: 他人と比較されるとやる気が下がる人が増えています。その人の過去と現在の成長・変化に注目して伝えましょう。
5. 感情的にならない: 自身の「〜あるべき」が破られると怒りが生じます。それゆえ、ネガティブフィードバックの際は感情的に相手をやり込めることのないようアンガーマネジメントしましょう。
6. 長々と話さない: よいアドバイスでも長時間にわたると説教になり、相手をうんざりさせます。特にネガティブフィードバックは、1回に伝える内容をひとつに絞り、要点を端的に伝えましょう。
7. 日頃から「ヨイ出し」をする: ポジティブなフィードバックを特別なときにだけ行うのではなく、日頃から些細なことにも目を向け、相手のよいところを伝えていく習慣をつくりましょう。
3.ビジネスシーンへの具体的なフィードバック
フィードバックは、多岐にわたる社内の人間関係や、組織が抱える多様な働き方の課題に対応するために応用できます。
3-1. 年上の部下への対応
年上の部下を持つケースは増えていますが、上司の役割として忖度しないことが大切です。ただし、相手の自尊心を傷つけない配慮が欠かせません。彼らの過去の成功体験を否定せず、「時代や組織の方向性の変化に合わせて変えてほしい」というスタンスで伝えましょう。また、彼らの持つ経験や能力をチームに貢献させるため、ポジティブフィードバックを通じて、彼らの存在がチームに役立っていることを具体的に伝えることが、活躍につながります。
3-2. ミスが続き改善の見込みがない人への対応
同じミスを繰り返す人への指導は、ミスの影響が周囲に迷惑をかけていること、そして会社や組織にとってのリスクと本人の将来的なデメリットの両方を伝えます。
それでも改善が見られない場合、指導を続けることに固執せず、視点をリスク管理に切り替えることも重要です。業務内容を柔軟に変更する、ダブルチェック体制を敷くなど、ミスを防ぐための仕組みを検討します。
3-3. 攻撃的なコミュニケーションをとる人への対応
仕事はできるがトラブルが絶えない、攻撃的なコミュニケーションをとる社員には、必要最低限のフィードバックに留めるのが得策です。彼らは自己受容度が低く、防衛のために攻撃的になる傾向があるため、人間性に関わる部分には深入りせず、業務上必要なことだけを端的に伝える関係性が有効な場合もあります。
3-4. 反応の薄い部下・自己肯定感が低い部下への対応
反応の薄い人には、「はい・いいえ」で答えられる質問を投げかけ、さらに「わかっているのか不安になるので、何でもいいから反応を返してほしい」と、こちらの気持ちを率直に伝えることも重要です。
自己肯定感の低い人は、褒め言葉を素直に受け取れず、過度な謙遜をすることがあります。また、「たまたまだ」「運がよかった」と成功を否定的に捉えるインポスター症候群という心理的傾向を持つ人もいます。この場合、抽象的な褒め言葉ではなく、具体的な行動や成果を挙げて伝えることが、相手に受け取られやすくなります。
3-5. 社外(取引先・クレーム対応)での応用
フィードバックは社内だけでなく、社外との良好な関係性を築くためにも有効です。
約束を破る取引先への対応では、受託側だからといってへりくだらないことが重要です。事実を確認し、約束を破ったことが業務にどのような影響を及ぼすのかを明確に伝えましょう。
ミスをする担当者には、責めたり批判したりせず、「今後、〜のように見直してもらえませんか?」と提案形式で伝えましょう。また、議事録や録音といった記録を残すことで、認識のズレを防げます。
感情的になっている得意先に対しては、相手の感情に振り回されず冷静に対応し、建設的な話し合いが難しい場合は、仕切り直しを提案する勇気も必要です。
4.「フィードバック」がもたらす組織への効果
フィードバックは、相手の成長のために改善をうながし、成長や可能性を広げる機会につながるものであり、健全な組織運営と人材育成の鍵となります。フィードバックとは、単なる指導やダメ出しで終わるものではなく、相手への「最高のギフト」です。
この「ギフト」を組織内で活用することで、個人とチームの成長促進、モチベーション向上、信頼関係の強化になり、組織パフォーマンスの最大化につながります。
フィードバックのスキルは、上司から部下へだけのものではなく、働くみんなが身につけておきたいコミュニケーションスキルです。日頃から、貢献してくれた人に積極的なポジティブフィードバックを伝え合う文化をつくること が、その第一歩となります。これにより、社内のコミュニケーションは、驚くほど円滑で心地よいものになるはずです。
近年、多くの企業で上司と部下による一対一の定期的な対話(1on1)が導入されていますが、その質を高め、部下の成長とエンゲージメントをさらに強化する『次の打ち手』としても、フィードバック研修の導入が注目されています。
貴社の人材育成、管理職のコミュニケーションの課題において、組織の成長と信頼関係の強化を加速させるための研修導入にご関心がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
ご相談は、下記フォームからお気軽にどうぞ。

■ 関連プログラム