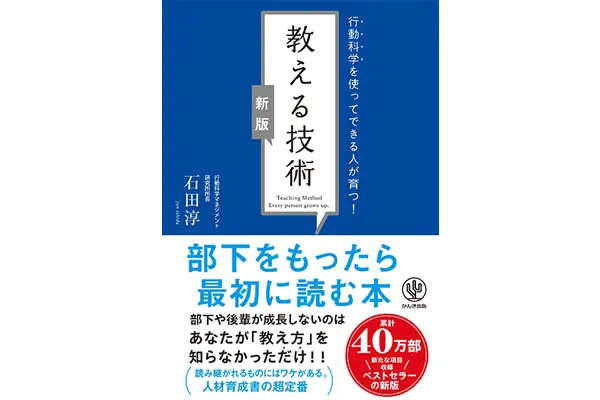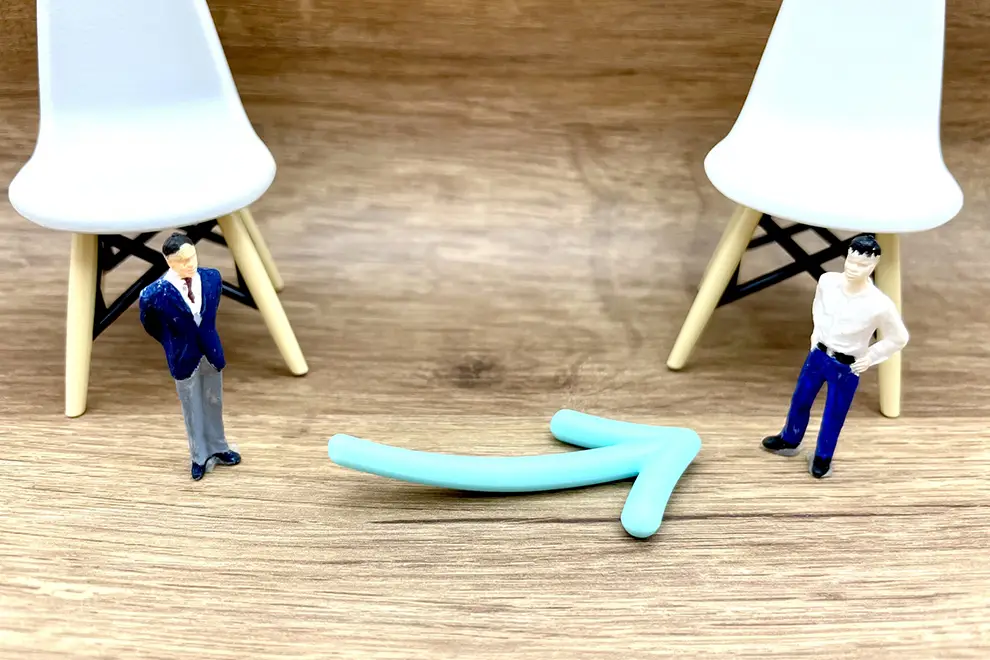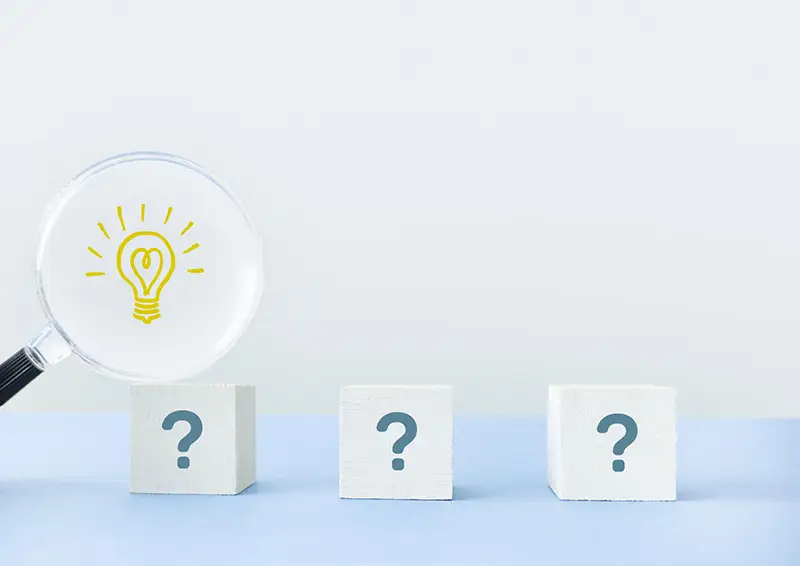目次
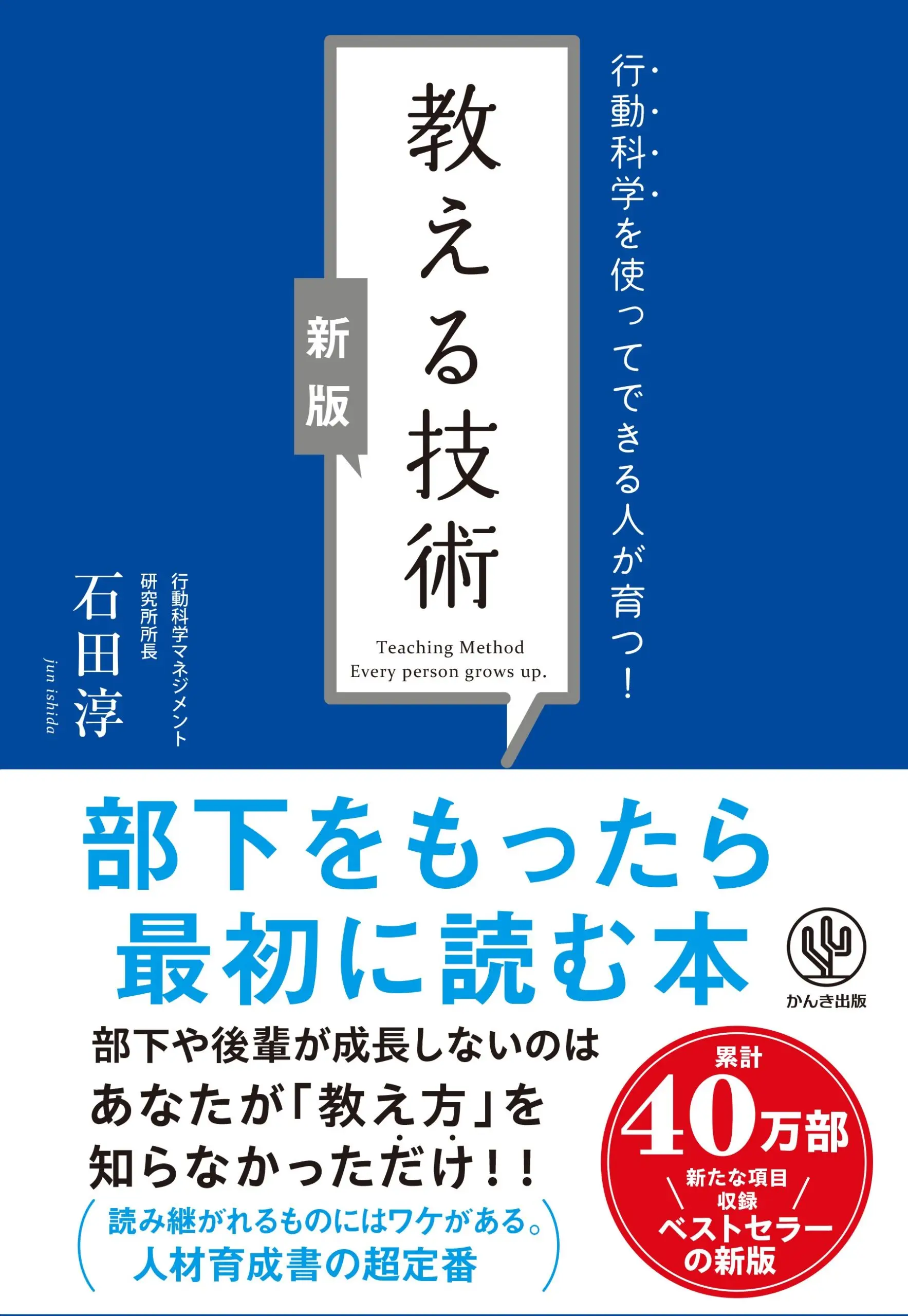 近年、働き方や価値観の多様化が進む中、従来の「見て盗む」指導や、上司の「センス・経験・勘」に頼ったOJTでは、若手や中途社員の育成が非効率になり、チームの成果が安定しないという課題が多くの企業で表面化しています。特に、 若手社員 の指導においては、従来の『心』に頼る指導法は通用しなくなっています。
近年、働き方や価値観の多様化が進む中、従来の「見て盗む」指導や、上司の「センス・経験・勘」に頼ったOJTでは、若手や中途社員の育成が非効率になり、チームの成果が安定しないという課題が多くの企業で表面化しています。特に、 若手社員 の指導においては、従来の『心』に頼る指導法は通用しなくなっています。
本書で紹介する『 行動科学マネジメント® 』は、行動分析学/行動心理学といった科学に裏打ちされたメソッドであり、結果ではなく「行動」に焦点を当てることで、「いつ、誰がやっても同じ結果が現れる(実験再現性)」ことを特徴としています。
本コラムでは、この科学的アプローチに基づき、企業の人材育成を劇的に変える「 教える技術 」の核となるポイントを解説します。
1. 「教える」前に心得ておきたいこと:なぜ心ではなく行動に注目するか
多くの管理職は、部下の育成がうまくいかない原因を、部下本人の「やる気がない」「真剣に仕事をしていない」といった心や精神状態にあると考えがちです。しかし、この考え方こそが問題解決を困難にしています。
行動科学マネジメント®の視点では、人が育たない原因は、教え手が「教え方」を知らない、習っていないという点に尽きます。ビジネスの成果や結果は、社員一人ひとりの「行動の集積」によって成り立っており、結果を変えたければ「行動」を変える以外に方法はありません。
つまり、 「教える技術」とは、相手から「望ましい行動」を引き出す 行為であり、感情論や精神論、人格を矯正することではありません。上司が心理学や精神医学の専門知識を持たず、多忙な業務を抱える中で部下の「心」を正そうとすることは極めて非現実的です。指導の軸を「心」から「計測・観察可能な行動」に移すことが、効率的な育成の第一歩です。
この科学的アプローチに基づく 「教える技術」 は、誰でも再現性をもって実践できるよう体系化されており、組織に導入する際は、具体的な手法を体系的に学べる研修プログラムを活用することが、マネジメントの属人的な負担を減らすことにつながります。
また、 教える技術 の効果を最大限に高めるためには、上司と部下の関係を築き、心理的安全性を確保し、「安心し仕事の話ができる土台づくり」が不可欠です。
仕事の成果を上げる組織は、コミュニケーションの量が3倍以上多いというデータがあり、離職率は上司とのコミュニケーションの量に反比例することが分かっています。まずは私的な話から入り、信頼関係を構築することが、指導の効果を高めるための基礎となります。
2. 上司がやるべきこと:短時間で成果を出すための「時間軸の矛盾」解消
管理職はしばしば、すぐに結果を求める「ビジネスの時間軸」と、数か月かかる「教育の時間軸」の矛盾に直面します。本書の「 教える技術 」のメソッドを実践することで、マネジメント層が部下育成にかかる時間を大幅に短縮できます。
育成を成功させるためには、管理職が部下の「仕事をする動機や目標」を把握することが必須です。現代の社員は価値観が多様化しており、「たくさん稼ぎたい」といった従来の動機だけではなく、「将来独立するためのステップ」や「家族との時間」など、個々人の目標を持っています。多様な社員に対応するマネジメントスキルとして、これらの個々人の目標に現在の仕事を結びつける「確立操作」を行うことが極めて重要です。この「確立操作」を行うことで、部下は自発的に望ましい行動を取りやすくなります。
また、管理職が自己の人間性を開示し、あえて失敗談を語ることも重要です。新人は上司を完璧な存在だと捉えがちですが、失敗のプロセスを共有することで共感が生まれ、指導を受け入れやすくなります。さらに、成功談ではなく失敗談を伝えることで、部下は「やってはいけないこと」を具体的に把握し、自ら有効な行動の道筋を探る(選択肢を広げる)ことができるようになります。
この戦略的なマネジメントアプローチは、管理職が教育とビジネスの二つの時間軸を両立させ、結果に直結する望ましい行動を引き出すために必須の 教える技術 です。
3. 部下のためにできること:教える内容の分解と具体的な言語化
属人化を排除し、誰でも成果を出せるチームを作るには、上司の「センス・経験・勘」を再現性のある「 行動 」として 言語化する ことが重要です。そのための具体的なステップは以下の通りです。
- 教える内容を「知識」と「技術」に分ける : 知識(知っていれば答えられること)と技術(やろうとすればできること)に明確に分類することで、指導手順の決定や、どこまで教える必要があるかの見極めが体系的に行えます。
- できる社員の仕事ぶりを「行動」に徹底的に分解する : 成果を出している社員の仕事ぶりを細かく観察し、具体的な行動をピックアップします。この分解作業は、その仕事を知らない人やできない人が、完璧にその行為を再現できるレベルまで細分化する必要があります。
- チェックリスト化と習熟度把握 : 分解された行動は「チェックリスト」として活用できます。このリストに基づき、部下が「どこまで知っているか」「どこまでできているか」をテスト形式(知識)やロールプレイング形式(技術)で確認します。これにより、その部下に教えるべきことが明確になります。
4. どう伝えるか:指示の曖昧さを排除する「MORSの法則」
部下への指示や指導が曖昧で抽象的だと、部下は何をすべきかわからず、結果として望ましい行動を引き出せません。例えば、「真心を込めて接客しなさい」ではなく、「商品を受け渡す際は必ず両手で渡し、お客様の目を見てから会釈し、3秒間静止する」というように具体化する必要があります。
行動を具体的に言語化する際に有効なのが、行動分析学で用いられる「 MORSの法則(具体性の法則)」です。MORSとは、以下の4つの条件を満たしていることを指します。
MORSの法則
| Measured (計測できる) | カウント、または数値化できる |
| Observable (観察できる) | 誰が見ても、どんな行動をしているのかわかる |
| Reliable (信頼できる) | どんな人が見ても、それが同じ行動だと認識できる |
| Specific (明確化されている) | 何をどうするかが明確になっている |
「売上を伸ばす」といった抽象的な目標を「チラシを毎週200戸に配布する」のように MORSの法則 に沿って行動に置き換えることで、教えるべきことが明確になり、客観的なチェックや評価も可能になります。
また、中間管理職にとって重要なスキルの一つが「翻訳作業」です。社長や上層部からの「一枚岩のような強い組織になろう」といった抽象的なメッセージを、現場の部下やアルバイトにも実行できる具体的な「行動」に変換して伝える必要があります。
さらに、長期目標を達成させるためには、達成感を得やすい「スモールゴール」を具体的に設定し、部下と一緒に一歩ずつクリアしていく環境を作ります。スモールゴールは「ちょっと頑張れば達成できる程度」の難易度が理想的です。
5. ほめることが大切:行動を定着させる「強化」の科学
管理職やマネジメント層にとって、部下に望ましい行動を「継続(定着)」させることが、人材育成の最終目標となります。この定着のためには、行動科学に基づいた「強化」が必要となります。
ビジネスにおいては、望ましい行動の直後に上司から「ほめられること」「認めてもらうこと」が最も効果的な強化剤となります。
なぜなら、新規営業のように、望ましい「行動」をしてもすぐに「結果」(契約)が出ない業務は多く、結果が出ないと行動の頻度は落ちてしまうためです。行動の直後に上司が評価を返すことで、部下は「上司はちゃんと見てくれている」と感じ、その行動が強化され、頻度が増えるのです。
教える技術 の原則に基づき、ほめる対象は、部下の人格や性格ではなく、あくまで 「行動」 でなければなりません。例えば、単に「真面目だね」とほめるのではなく、「昨日の会議資料を、期限までに誤字脱字なく完璧に提出した行動は素晴らしい」といった 具体的な行動に焦点を当てる ことが重要ですのです。
一方、「叱る」ことは相手の行動を改善するために必要ですが、「怒る」(感情的な行為)とは異なります。叱る場合も、人格ではなく具体的な 「行動」 に焦点を当て、叱りっぱなしにするのではなく、 行動変容 のための具体的な道筋を示すフォローがセットで必要です。
この行動科学に基づいた 「強化」 の原則は、研修を通じて管理職が実践することで、組織全体の再現性の高い人材育成につながります。
6. 継続させるために:モチベーション神話の否定と行動の計測
マネジメントにおいて、「モチベーション」や「やる気」といった曖昧な言葉に頼って部下を判断してはいけません。それらは計測・観察可能な行動ではないため、育成の非効率性につながるからです。
望ましい行動を継続させるためには、メジャーメント(計測)と定期的なフィードバックが不可欠です。
- 行動の数の計測 : 部下自身に、結果に直結する望ましい「行動」の回数(例:特定のリスクの高いリストへの訪問数)を記録させ、グラフ化することで、成果が出ていなくても努力の跡を可視化させます。
- 定期的なフィードバック : 計測した行動の記録を少なくとも2週間に1回は上司と部下が一緒にチェックします。行動の強化は、行動の直後(理想は60秒以内)に行うのが最も理想的ですが、大人の場合、最長2週間以内であれば強化の効果が持続することが実験で判明しています。フィードバックを通じて行動を評価し、望ましい行動を継続的に強化することが、部下の成長をサポートします。
教える技術 の最終段階として、部下が自立できるようになるために、指導の過程で与える補助(ビート板や補助輪にあたる)である 「プロンプト」 をいつか外す 「フェイディング」 が必要です。管理職がいつまでも外部との打ち合わせに同席したり、資料作成の構成を渡したりする「補助輪をつけたまま走らせ続ける」行為は、部下の成長や自立を阻害します。
管理職は、計測に基づき部下の行動の習熟度を把握しながら、適切なタイミングでフェイディングを実施することが、真の自立型人材育成につながります。
7. こんな場合はどうするか:多様な社員(年上部下、中途、リモート)への対応
年上部下の 指導
年上部下を持つ場合、「上司と部下=上下関係ではない」という発想が大切です。両者の関係は、チームをまとめる人と現場で成果を上げる人という「ポジションの違い」でしかないと捉え、互いの長所を活かす姿勢で臨むことが、指示指導の迷いを払拭します。
中途社員の育成
即戦力として期待される中途社員に対しては、過去の経験があるからこそ、現職場の「知っていること/できること」を詳細に割り出します。加えて、以前の職場で有効だった行動の中に、あなたの会社では「やらないこと(劣後順位)」を明確に示してあげることも徹底しましょう。
ハラスメントと 指導
ハラスメント問題を避けるためにも、指導は「相手の『行動』のみに焦点を当てる」という基本原則を徹底する必要があります。人格や性別、育ち方など、業務に関係のないことに言及した叱責は絶対に避け、改善してほしい具体的な行動のみを指摘します。
リモートワークでの信頼関係構築
リモートワークではコミュニケーションの量が減り、部下の行動の修正が困難になります。信頼関係を築き、行動を強化し続けるためには、「コミュニケーションの頻度」を重視すべきです。心理学の「ザイアンスの法則」にもある通り、接触回数が多いほど親近感を覚えます。
リモート環境だからこそ、上司は毎日1分間、部下と話す「1分ミーティング」の習慣を取り入れ、積極的に声かけを行う必要があります。
おわりに:科学的手法による「教える技術」の体系化は、組織成長の必須条件
現代の企業経営において、希少な人材をスピ―ディに育成し、成果を出す仕組みを持たない組織は淘汰される時代です。
「 行動科学マネジメント® 」に基づく再現性の高い 教える技術 を組織に導入することは、マネジャーの属人的な負担を減らし、「教えられる側、教える側双方に負担のかからない効率的なマネジメント」を実現します。
この科学的メソッドを習得すれば、育成にかかる時間を大幅に短縮し、部下は「望ましい行動の強化」によって自ら成長を望む自立型の人材へと変貌します。そして、人を育てることができる人こそが、本物のリーダーとなり、人材育成の大きな喜びを体感できるでしょう。
このコラムでご紹介したメソッドを、あなたの組織の課題解決に役立てるために、具体的な手法を体系的に学べる研修プログラムをご用意しております。
アーカイブセミナー開催中
“できる社員” を育てる『教える技術』デモセミナー
現在、本プログラムの導入意義やワークの一部を体験できるデモセミナーのアーカイブ配信を無料で公開中です。行動科学マネジメント®の考え方や、研修カリキュラム例、対象別( 若手 ・中堅・管理職)の展開方法をご確認いただけます。
視聴期限:2025年12月26日(金)17:00まで
お申込み・詳細は【セミナー詳細・申込ページへ】
お問い合わせ
ご相談は、下記フォームからお気軽にどうぞ。

■ 関連プログラム