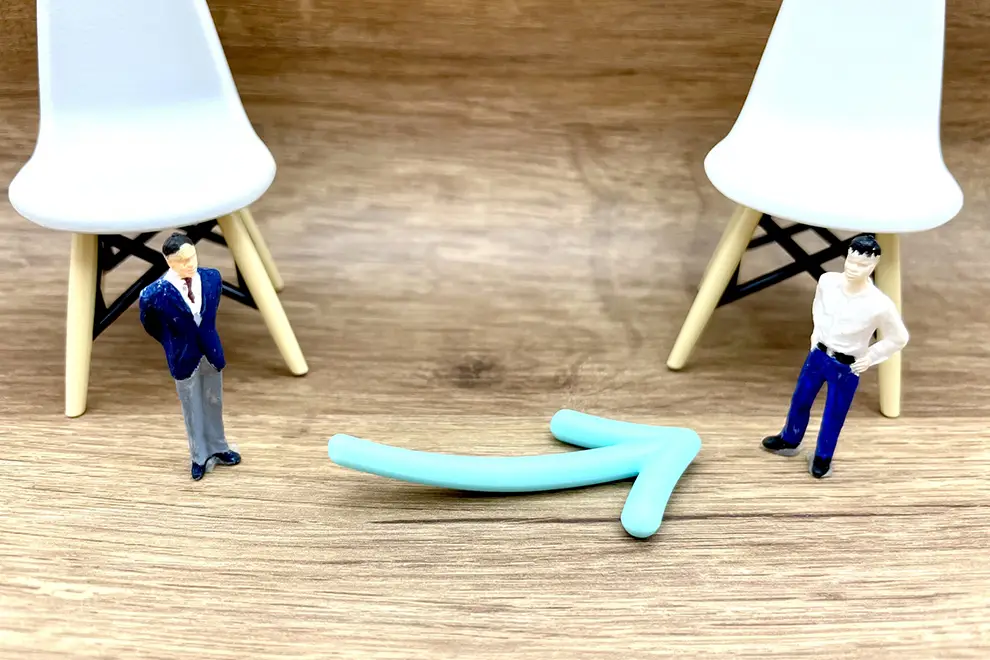目次
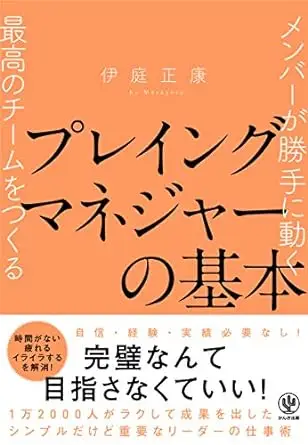 日本の課長職の99.5%がプレイングマネジャーと言われ、その多くの悩みが「部下と対話する時間がない」「チームマネジメントが不十分になっている」という“忙しさを乗り越えられない”といったものです。
日本の課長職の99.5%がプレイングマネジャーと言われ、その多くの悩みが「部下と対話する時間がない」「チームマネジメントが不十分になっている」という“忙しさを乗り越えられない”といったものです。
そんな悩み、課題をもつプレイングマネジャーに最も不可欠なスキルは「任せる力」です。それも、大胆に部下に仕事を任せる。そのことによって、大胆に業務も効率化でき、リーダー自身の仕事はもちろん、チーム運営の業務も積極的に部下に託しながら、全員でチームのパフォーマンスを高めることができるようになるのです。
本コラムでは、拙著『メンバーが勝手に動く最高のチームをつくる プレイングマネジャーの基本』から、まずは、プレイングマネジャーと専任マネジャーの違い、プレイングマネジャーがどんな課題をもっているかについてあらためて整理します。続いて部下に大胆に仕事を任せていくために必要なプレイングマネジャーの心構え・マインドセット、具体的な仕事の任せ方や業務の効率化について紹介していきましょう。
プレイングマネジャーとは?-プレイングマネジャーと専任マネジャーの違い
プレイングマネジャーは、専任マネジャーと違って、自身のプレイヤーとしての業務と部下マネジメントの両方を行う必要があり、一般的に「リーダー」「マネジャー」と呼ばれるマネジメント専業の仕事と本質的な違いがあります。そのため、専業のマネジャー向けのノウハウを伝えるだけではやることばかりが増えてしまうのです。
プレイングマネジャーの課題・研修の必要性
「常に忙しくて、時間に追われている」「細かく指示を出さないと部下が動いてくれない」「仕事を任せたくても、部下が育たない」「残業が禁止されているので、家に持ち帰る仕事が増える」など、プレイヤーとしての業務とマネジメント業務の両立が難しく、悩みが尽きません。自分の目標数字だけではなく、チームの数字も課せられているため、常に最前線でプレイヤーとしても動く…。その結果、部下とのコミュニケーションが希薄になり、チームの雰囲気が険悪になるという悪循環に陥ります。
チームマネジメント、時間管理、コミュニケーション、ティーチング、エンパワーメントなど様々なメソッドを組み合わせたノウハウを得ることで、チームの状態が向上し、仕事を任せられる部下が育ち、成果が出るチームへと変化します。
プレイングマネジャーの5つの心得
【心得1】「自分でやってしまいたい」を捨てる
プレイヤーとして実績がある人ほど、「自分でやってしまいたい衝動」に駆られやすい傾向があります。この衝動が「いつも忙しい」「部下が育たない」という悩みを引き起こす原因です。プレイヤーとしての業務を「自分の魅せ場」と思い、業務を抱えがちなので、まず「部下の力を借りる」と決めましょう。プレイングマネジャーは、なんでも自分でやろうとしがちですが、それはプレイヤーの発想です。マネジャーの発想に切り替えるという意識改革から始めましょう。
【心得2】任せられるマネジャーは、“今”ではなく“1年後”に視点を置いている
部下に任せると、いちいち説明したり、ミスが起こらないよう確認したりするため、時間がかかるため、「自分がやった方が早い」と思いがちです。しかし、この先チームの規模が大きくなったり、仕事が増えたりした場合には、仕事がまわらなくなることは明らかです。プレイングマネジャーは、目先のことに捉われず、物事を中長期視点で考えることが重要です。
【心得3】ブレない判断基準を持てば、業務量を3割減らせる
仕事を任せされた部下は忙しくなるため、プレイングマネジャーは仕事を任せるだけではなく、チーム全体の仕事量を3割削減することも合わせて考えます。過去の延長線上ではなく、基準を設け、業務改革を行いましょう。
無駄かどうかの判断基準は
①顧客満足に悪影響が出る
②従業員満足に悪影響が出る
③コンプライアンス上の問題が発生する
の3点です。このうち一つも当てはまらない業務はなくします。
【心得4】あなたがいなくても勝手に動くチームを目指せ
自分のプレイヤーとしての業務を部下に引き継ぐだけではなく、マネジメント業務の一部も引き継ぐことで、「自主運営型」のチームになります。「自分がいなくてもメンバーが勝手に動くチーム」です。そのためには、チーム内に参謀役的なミニリーダー「連結ピン」を置くことが有効です。権限移譲によって、プレイングマネジャーのマネジメントの負担を軽くしながら、部下の主体性を高められるチームに成長します。
【心得5】「仕事がまわる」がゴールではない。現場からイノベーションを目指せ
自分の仕事を部下に任せ、無駄な仕事をなくし、自主運営型チームに変えただけでは、プレイングマネジャーの業務として十分ではありません。現場を知るプレイングマネジャーだからこそできる、新しい挑戦を企て、成果を上げることを目指しましょう。
そのために挑戦することは次の2点。
・お客様の要望に応えるだけではなく、期待を超えるサービスに挑戦する
・部下に高い期待をかけ、部下のキャリアの可能性を広げる
現場で発生する「不満」「不安」「不便」の声は、イノベーションのヒントになります。現場の最前線にいるプレイングマネジャーだからこそ、「3つの不」をいち早くキャッチし、対策を講じることができるのです。
プレイングマネジャーの仕事術
【1】誰にでも不安なく引き継げる仕事の任せ方
部下は必ずミスをします。部下にミスをなくす努力を求めることよりも大切なことは、プレイングマネジャー自身が失敗への許容度を高めておくことです。前提を変えれば、失敗に寛容になれます。
発生確率と仕事に与える影響の大きさでレベル分けし、予防策・事後対処法を予め決めておきます。発生確率と影響度の大きいものだけを手を打っておきましょう。
ミスの多い部下にはティーチングの技法を用いて、「細かく伝える」「不安や不明な点がないか尋ねる」「最後に復唱してもらう」の3ステップで部下の思い込みやうっかりミスを防ぎましょう。
また、完璧主義のプレイングマネジャーは、部下の成長を止めてしまいます。上司の「適当力」が部下の工夫を引き出しますので、「これで事足りるだろうか」のポイントを重視します。Must条件とWant条件を明確に分けて部下に伝えることで、部下は何をすればいいかを自分の裁量で決めることができるのです。
【2】無駄を削減し、効率を上げるチームの仕事の減らし方
手間をかけることが「いい仕事」ではありません。仕事を減らすことは「最高の仕事」を追求するために必要なことです。効果に影響しないことはやめる。この考え方を「合目的的」といいます。目的に照らし合わせ、効果のあることのみに集中することです。
無駄なことは、フレームに当てはめることで見つけることができます。おすすめのフレームは「ECRS」です。
・E(Eliminate・排除):業務そのものをなくすことはできないか?
・C(Combine・結合):複数の業務をまとめることはできないか?
・R(Rearrange・順序変更・交換):作業の順序を変えられないか?
・S(Simplify・単純化):作業内容をもっと簡単にできないか?
この4つの観点からプレイングマネジャーの業務と、部下の業務を含めたチーム全体の業務を減らしていくと、マネジメントは省力化できます。
【3】プレイングマネジャーがいなくても仕事がまわるチームのつくり方
プレイングマネジャーは。ずっと自席に座っているわけにはいきません。自分が不在のときでも、部下一人ひとりが自分で考えて、行動できるようにしておく必要があります。ここで大切なことは、マネジャーが「こうあるべき」と考える行動指針を明確にしておくことです。キャッチフレーズにし、チームに浸透させておきましょう。
また、チームの一体感を高めるために、「何のために仕事をして、何を成し遂げるのか」を掲げます。自分たちのためではなく誰かのため、何をどのように変えたいかというBefore・Afterの考え方、使命感の観点で、具体的な「未来予想図」を語り、チーム全員の目的を合致させましょう。
お問い合わせ
ご相談は、下記フォームからお気軽にどうぞ。

■ 関連プログラム