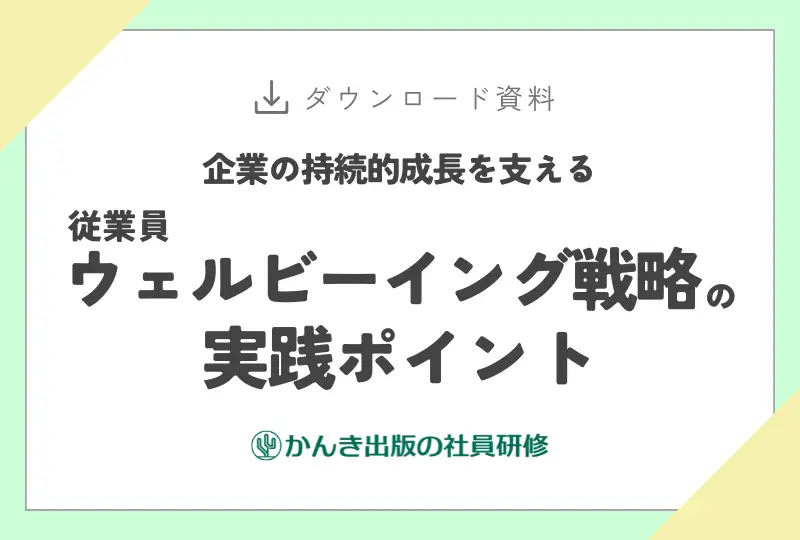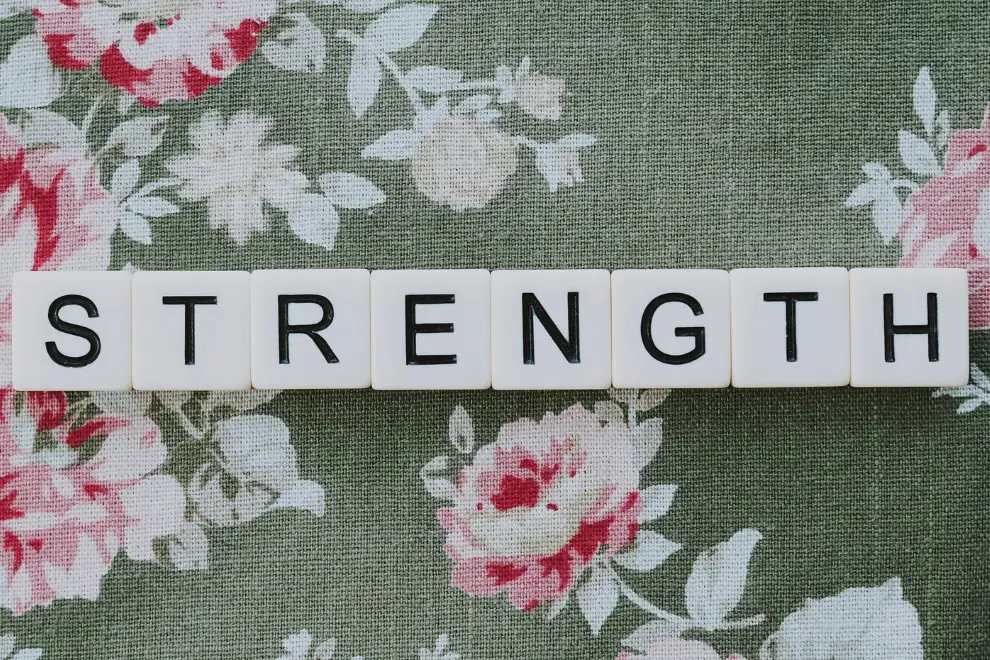目次
はじめに
ここ1〜2年、企業におけるウェルビーイングの重要性はかつてないほど高まっています。
従業員の幸福度を高めることは、単なる"やさしさ"ではなく、エンゲージメント向上や離職率低下を通じて、ウェルビーイング投資のROIを高める戦略的な取り組みです。
しかし、実際に研修やプログラムを導入した担当者からは、こんな声も聞かれます。
- 「取り組んではいるが、成果をどう測ればいいのか分からない」
- 「"良い取り組み"で終わってしまい、経営層にROIを説明できない」
本記事では、ウェルビーイング研修を戦略的投資として設計・運用する方法を解説します。
また、2026年に向けた最新トレンドや施策設計のポイント、効果測定の手法についてもまとめています。
■ 関連資料ダウンロード
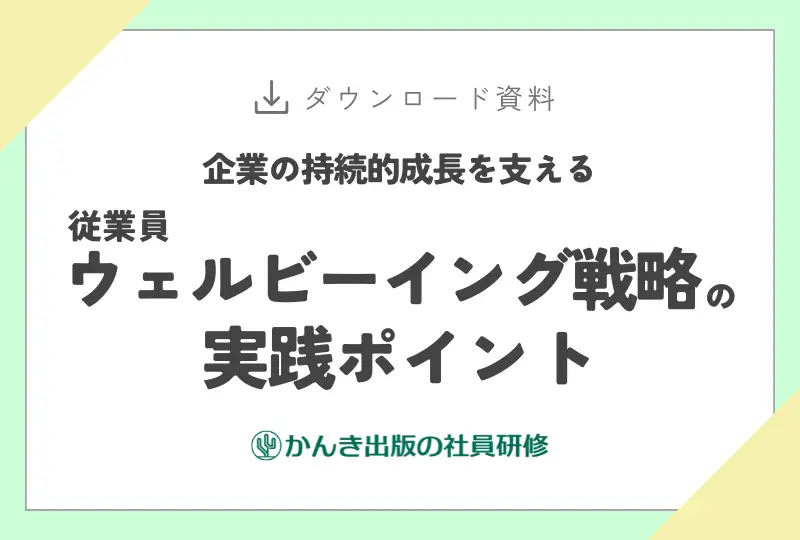
ウェルビーイングが「戦略的投資」とされる理由
かつてウェルビーイングは福利厚生の一部と捉えられていました。しかし現在、世界の潮流は明確に変わりつつあります。
Gallupなどの調査では、ウェルビーイング投資を行う企業で、
- 病欠が53%減少
- 離職意向が32%低下
というデータが報告されています。
また、Willis Towers Watsonの調査では、従業員体験(EX)の強化について、過去3年間で進捗があった企業は34%に留まったものの、今後3年間で強化が重要であると考える企業の割合は72%に上るとされています。
企業にとってEXは将来の最優先事項であり、その実現の中核にウェルビーイングの強化が位置づけられています。
こうした背景から、ウェルビーイングへの投資は単なる"やさしさ"ではなく、人材定着と生産性向上を両立させる戦略的経営施策として注目されています。
従来の福利厚生では通用しない:新しいウェルビーイング投資の考え方
従来の福利厚生は、医療保険や通勤手当など"最低限の安心"を提供するものでした。
しかし今の職場環境では、それだけでは従業員を支えきれません。
- リモート・ハイブリッドワークの定着で「孤立」や「つながりの希薄化」が進行
- 若手層の価値観が「安定」から「成長」「意味のある仕事」へシフト
- メンタル不調への対応が事後対応中心で、予防的支援が追いつかない
こうした中で、ウェルビーイングは報酬以外の価値提案(EVP)の中核として重視されています。
企業はもはや「安心の提供」ではなく、「成長・つながり・心理的安全性」を支える仕組みをウェルビーイング研修などの形として整える時代にあります。
ウェルビーイングとエンゲージメント:若手社員の離職率低下のカギ
多くの人材開発担当者が頭を悩ませているのは、若手社員のエンゲージメント低下と離職率の高さです。
「安定はあるが、やりがいが感じられない」
「自分の成長実感がない」
こうした声が組織の活力を奪っています。
Gallupの分析によると、エンゲージメントの高いチームは、低いチームに比べて収益性が約23%高く、生産性も約14%向上しています。
また、離職率も改善され、高い離職率の組織では21%の低下が確認されるなど、明確な成果が報告されています。
ウェルビーイング研修は、こうしたエンゲージメント向上の起点になります。
特に若手社員のメンタルヘルスサポートを意識した内容にすることで、離職予防効果が高まります。
具体的には、以下のような研修を段階的に組み合わせることで、若手社員の自律的成長を促します。
- マインドフルネス研修:今ここに意識を向けることで、集中力や感情のコントロール力を養い、ストレスに強い基盤を作る
- ストレスマネジメント研修:日常業務での感情のセルフマネジメントを学び、自己効力感を高める
- レジリエンス研修:困難や失敗を成長の糧に変える思考習慣を身につけ、前向きに行動できる力を育てる
これらは単なる「リラクゼーション」ではなく、若手が自分の仕事に意味を見出すための内省の機会です。
結果として、離職率低下や生産性向上といった具体的な経営成果につながります。
ROIを可視化する:ウェルビーイング投資の効果測定の仕組み
経営層を動かすには、"数字"が欠かせません。
ウェルビーイング施策のROIを説明するためには、定量的な効果測定とPDCA運用が重要です。
代表的な指標:
- エンゲージメントスコア(パルスサーベイ・年次調査)
- 離職率・病欠率・1on1実施率
- 研修前後の心理的安全性・自己効力感スコア
これらを「施策 → 指標改善 → 生産性向上」というストーリーで示すことで、経営層の理解を得やすくなります。
また、『人的資本可視化指針(内閣官房)』や国際基準(ISO 30414)により、今後はウェルビーイング施策の効果指標の開示も求められる見込みです。
成果を出すウェルビーイング研修の設計方法
ウェルビーイング研修を成果につなげるには、「単発イベント」ではなく戦略的プログラム設計として実装することが不可欠です。
- 現状把握:定量データ+離職理由などの定性情報を分析
- KPI設定:「若手離職率○%改善」「エンゲージメントスコア+0.3向上」
- 研修テーマの組み合わせ:ストレスマネジメント/マインドフルネス/レジリエンス/コミュニケーションなどの相互補完型構成
これらのプロセスを体系化したウェルビーイング研修プログラムを導入することで、エンゲージメントと生産性を同時に高めることができます。
研修の狙いは「癒し」ではなく、自律的に変化できる人材を育てることです。
このようなアプローチが、企業の競争優位性を確立するカギとなります。
かんき出版が支援する戦略的ウェルビーイング研修
出版社として長年にわたりビジネストレンドを発信してきたかんき出版の社員研修は、ウェルビーイングを一過性の流行ではなく、人と組織の成長戦略として捉えています。
特徴:
- トレンドと実践を融合したカリキュラム設計
- 高いカスタマイズ性(企業課題に応じたオーダーメイド)
- 年間実績850件超:製造・IT・金融など、幅広い業界をご支援
■関連研修を見る
心とからだと働き方を整える「ウェルネスライフセミナー」
「今」の状態を正しく認識し、集中力を高める「マインドフルネス研修」
立ち直る力/やり抜く力/ストレス耐性をつける「レジリエンス研修」
最後に:ウェルビーイングはやさしさではなく戦略
ウェルビーイング研修は、単なるメンタルヘルス支援ではなく、企業の持続的成長を支える戦略的投資です。
重要なのは、施策を「実施して終わり」にせず、定量的な効果測定とPDCA運用を組み込み、経営層にROIを説明できる形にすることです。
こうすることで、
若手社員の離職率低下やエンゲージメント向上、組織全体の生産性改善
といった具体的成果につながり、ウェルビーイングが企業戦略の中核であることを証明できます。
今こそ、ウェルビーイングを戦略的投資として再設計し、企業の成長に直結させるチャンスです。
■ ウェルビーイング研修・施策設計のご相談

■ 関連資料ダウンロード